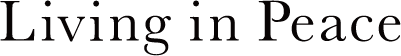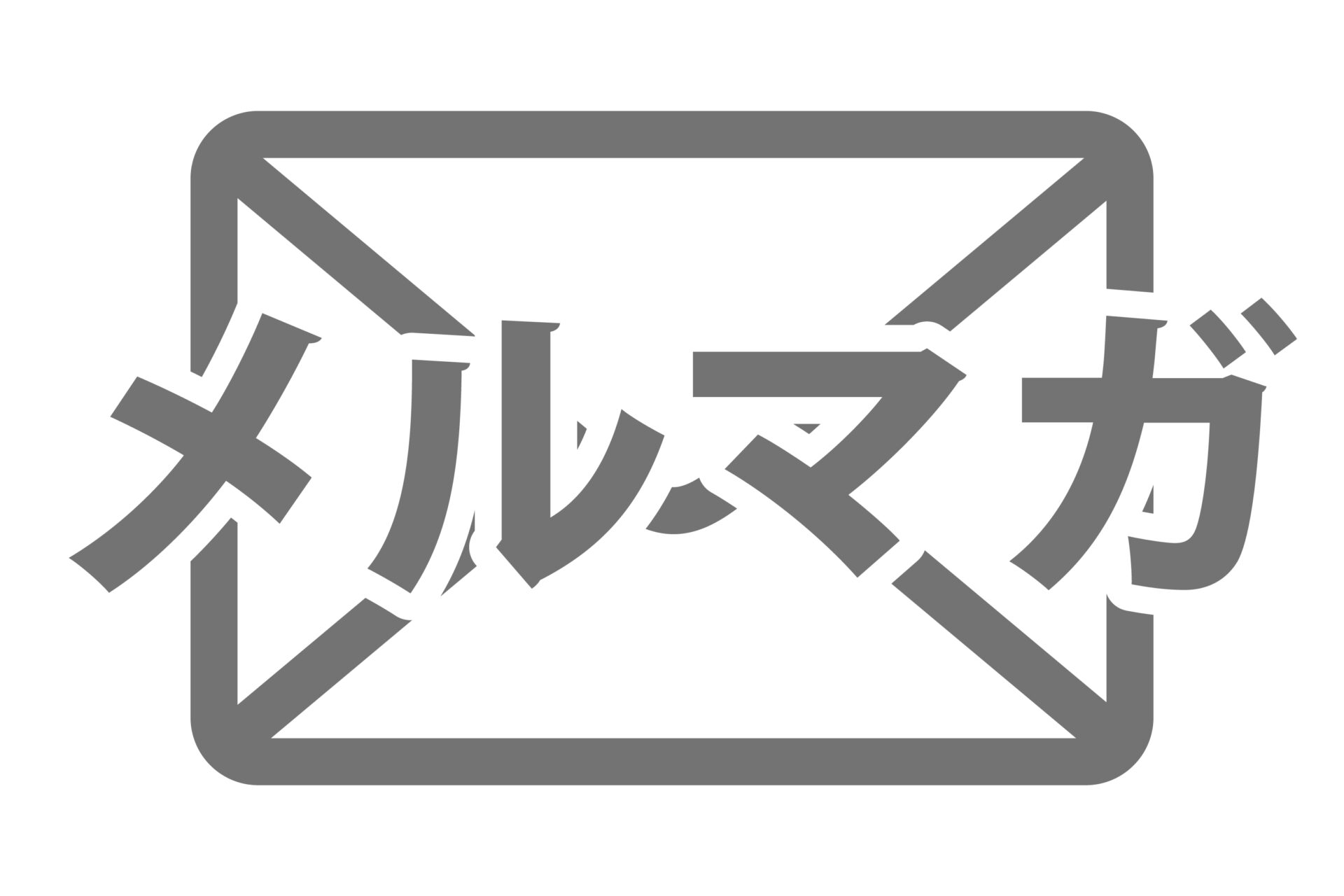2025年1月24日、認定NPO法人Living in PeaceとISI日本語学校(運営:株式会社WEWORLD)が、オンラインイベント「教育の力で社会を動かす:ISI日本語学校が実践する難民支援のカタチ」を共催しました。
本イベントでは、日本における難民支援の現状や課題、Living in Peace (以下、LIP)とISI日本語学校(以下、ISI)が共同で提供する日本語学習プログラムの成果、そして今後の展望について紹介されました。また、より多くの日本語学校が難民支援に参加できるよう、具体的な取り組みや支援のあり方について議論が交わされました。本記事では、その内容を抜粋してお届けします。
日本語学校での難民受け入れから見えた課題と可能性
他の受講生との違いはあるのか?
イベントでは、難民背景を持つ生徒と他の受講生との違いはほとんどないという意見が出ました。実際、ISIの授業を担当する講師の中には、生徒が難民であることを知らないまま教えているケースも少なくないとのことです。「日本語教師の立場からすると、生徒が難民であるか留学生であるかは大きな違いではなく、“日本社会での基盤を築くための支援ができること”自体が意義深い。」という声が現場の講師の方から寄せられました。
オフライン授業のメリットと課題
「難民の中には地方在住者も多く、オフライン授業の場合、校舎から遠い学生は長期的な学習継続が難しくなる、あるいは受け入れそのものが困難になる」という課題については、「ISIだけでなく複数の日本語学校が難民を受け入れることで、学習継続がしやすい環境を整えることができるのではないか。」と難民の日本語学習支援の輪を拡大する方向が示されました。
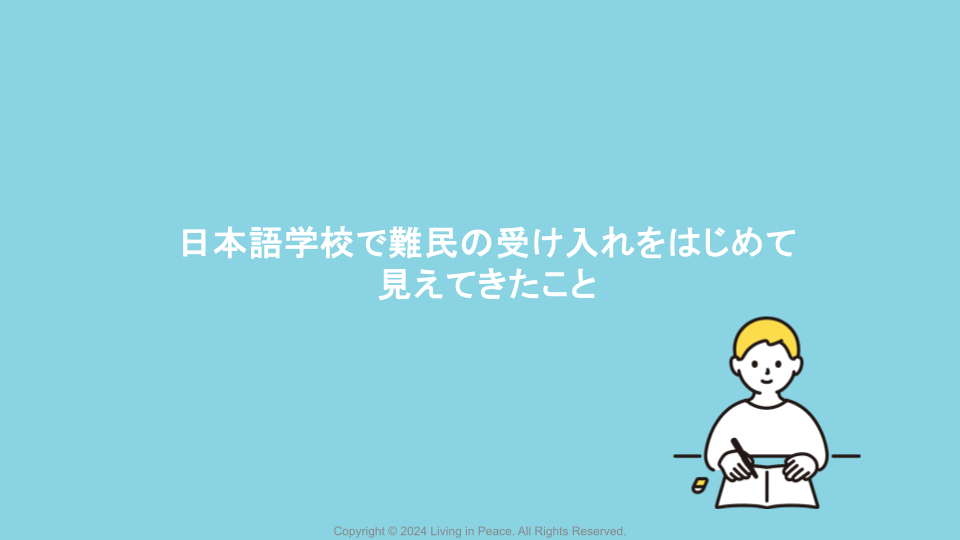
一方で、オフライン授業には多様性のある学びの場を提供できるという大きなメリットもあります。異なるバックグラウンドを持つ学生同士が交流する機会が生まれ、多文化理解が促進されることが期待されています。「日本語学校は社会的な認知度が低いものの、難民支援という分野では独自の社会貢献ができる」という点を強調した意見がISIの担当者からありました。また現場の講師からは、「日本語学校での学びが、日本社会で暮らしていく上での”居場所”のひとつになる」との意見も聞かれました。
今後の課題と必要な支援
ISIでは、日本語学習後の就職支援の充実や他の日本語学校との連携強化を今後の重要課題と考えています。現在入国管理局告示基準に準じた日本語教育では、対面授業が必須とされており、提供できる教育の環境が限定的となっています。「現在、ISI日本語学校グループは8拠点で難民支援を行っておりますが、より多くの日本語学校と協力し、学習環境の選択肢を広げていきたい。」とのことです。
日本社会への展望
世界的に移民が増加する中、ISIでは単なる言語指導にとどまらず文化や社会制度を教えることも実践しており、このような取り組みは移民問題の解決の一助となると考えられます。20年以上のキャリアを持つ日本語教師からは、「ISIで仕事をする中で難民支援に携われることは誇りに感じる」「日本語学校には多様な人材が集まっており、今後さらにその数が増えると良い」との言葉もありました。
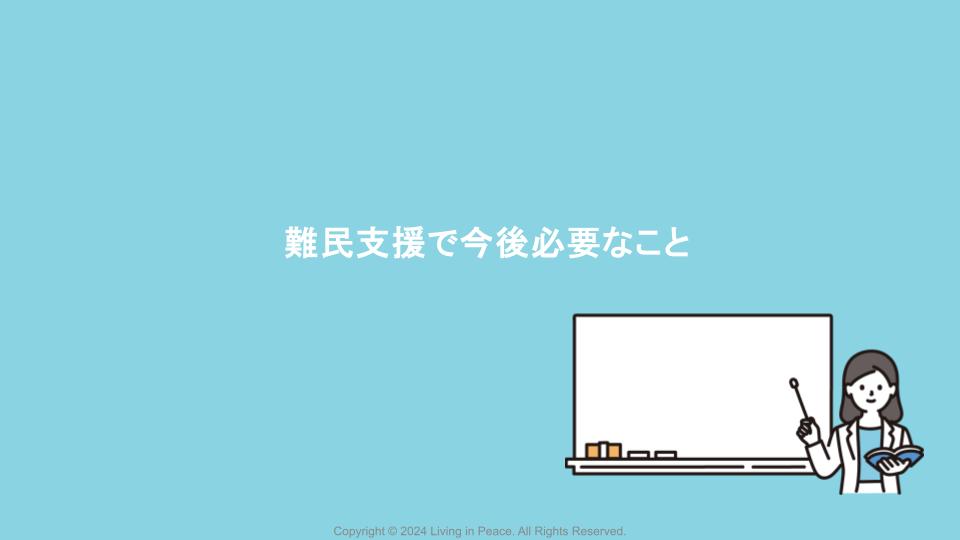
参加者との質疑応答
イベントの後半では、参加者から多くの質問が寄せられ、日本語学校における難民支援の具体的な取り組みについての関心の高さがうかがえました。その中でも特に重要なポイントとなった質問とその回答を以下にまとめます。
難民性の判断基準について
Q どのようにして難民としての資格を判断しているのか?
A LIP-ISIプログラムでは、難民の認定証有無だけでは、日本で難民認定される数少ない人々しか支援の対象とできないため、LIPのネットワークを活用し、難民支援団体等から難民の背景を持つことを証明できる人々も対象としています。
クラス分けの基準について
Q 宗教や国籍の違いによるクラス分けは行っているのか?
A ISIもLIPが独自に提供するLIP-Learningにおいても、原則として特別なクラス分けは行わず、すべての学生を同じ条件のもとで受け入れる方針を事前にお伝えしたうえで本人の意思に任せる形をとっています。
関東以外のNPOとの連携について
Q ISIやLIPの拠点は関東が中心だが、関東以外の地域に住む難民の学習機会はあるのか?
A LIPが独自に行うLIP-Learningではオンラインで日本語学習支援を提供しているので、地方に住む方も利用できます。また提携先である「にわとりの会」は愛知県小牧市を拠点に活動しています。今後もこうしたオンラインや地方拠点の企業・NPOとの連携を強化し、より多くの地域で学習機会を提供できるようにしていきたいと考えています。
難民の受講料負担について
Q 難民の受講料は誰が負担しているのか?
A 現在、LIP-ISIのプログラムではISIが難民の受講料を負担しています。ISIを代表事例とし、LIPや他の難民支援団体も協力して様々な日本語学校がこの取り組みを真似できる仕組みの構築が今後必要になってきます。
まとめ:教育の力で社会を変える
今回のイベントでは、ISIとLIPの取り組みを通じて、日本語教育が難民支援にどのように貢献できるのかを具体的な事例を交えて紹介しました。
日本語教育は、難民の方々が日本で自立し社会に溶け込むための重要なツールとなります。さらに、日本語学校とNPOが連携することで、より効果的な支援体制を構築できる可能性が高まります。
ISIやLIPに興味を持たれた方は、ぜひ以下のリンク先よりお問い合わせいただけますと幸いです。
LIPと連携して難民支援を検討する日本語学習機関についてはこちら
日本語学校としての難民支援のノウハウのご相談先はこちら
LIPメンバーとして活動に興味がある方で詳細を知りたい方はこちら
ISIの日本語教師に興味がある方で詳細を知りたい方はこちら