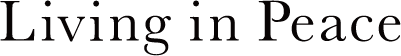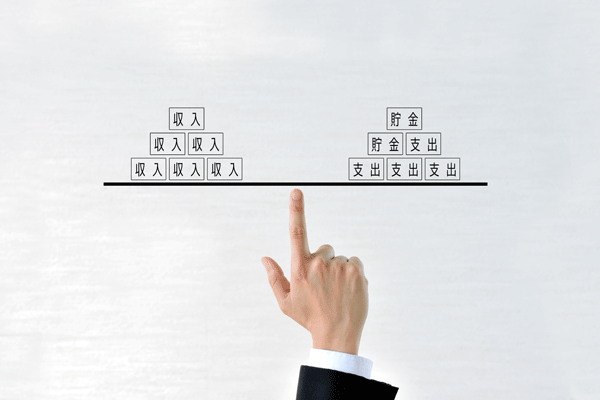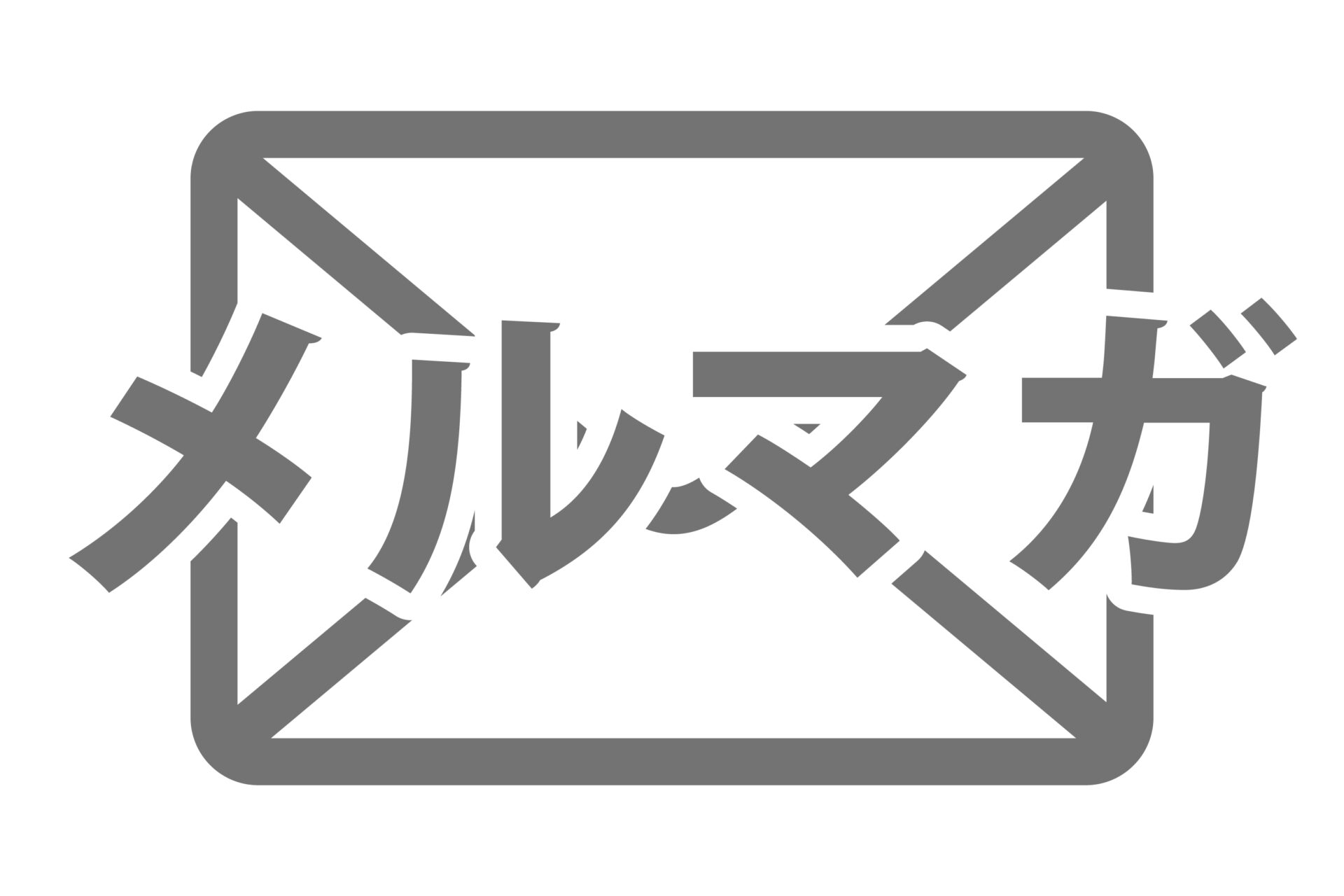こどもプロジェクトChance Maker奨学金事業は、2025年3月 奨学生1名の卒業をもって奨学金の給付が完了しましたのでお知らせいたします。
Chance Maker奨学金事業の歩み
<事業開始の背景>
Chance Maker奨学金事業は2015年度に開始しました。
当時、全国的に大学・専門学校への進学率が約8割に達するなか、児童養護施設出身者の大学・専門学校への進学率は2割強でした。児童養護施設出身者の進学率が低い背景には、児童擁護施設は原則として18歳で退所しなければならないため、進学するためには自分ひとりで生活費だけでなく学費も稼ぎながら、勉強を続けなければならないという難しさがありました。
そのためLiving in Peaceこどもプロジェクトでは、「すべての子どもに、チャンスを」という理念のもと、経済的理由により生じる進学の課題解決を目的とし、社会的擁護下の子どもたちの高等教育への進学を給付型奨学金の形で支援してきました。
当奨学金は下記2点の実現を目指し、家賃補助として月額3万円を給付することからスタートしました。
・経済的理由により進学が困難な子どもが、進学・卒業し社会で活躍できるようになること
・同じ境遇にある子どもたちが先輩の姿を見て、自分にも進学の選択肢があることに気付けるようになること
<見えてきた課題>
その後、受け入れた奨学生の多くが、進学をしても大学生活を続けることができないという問題に直面することになりました。健康上の問題や自分ひとりでお金の管理ができなかったなど、その理由は様々です。
特にお金については、収入の問題の他に管理についても高いハードルがあります。(お金に関することは身近な人にも相談しづらい内容です。また、使い込みに気がつき注意ができる人が近くにいないことがほとんどです)
また、一人暮らしや進学先での困りごとも、施設にいた頃と違って自分の力で解決しなければなりません。奨学生には金銭面の他にも、さまざまな面からのサポートが必要とされていることが改めて明らかになりました。(※2015〜2017年に採用した6名の内、4名が中退をしています。)
<課題に対しての施策と結果>
そこで我々は、2019年度より「お金の教育」と「フェローシッププログラム」という2つのサポートをスタートすると同時に、奨学金の増額をしました。
1)「お金の教育」
奨学金の面接時に大学4年間を通してどの時期にどれぐらいのお金が必要か、またアルバイトでは1ヶ月にどのぐらい稼ぐ必要があるかなど、資金シミュレーションを一緒に実施しました。奨学金の支給開始後も半年に一度同じシミュレーションを行い、今の収支から卒業時の貯蓄予定額を見えるようにすることで、奨学生自身にお金を管理する力が身に付くよう伴走しました。
2)「フェローシッププログラム」
下記の3点を主な目的とした奨学金の伴走プログラムです。
・当メンバーと奨学生の親密な関係を構築し、いつでも相談しやすい環境をつくる
・プログラムを通じて、奨学生の自己肯定感を醸成する
・様々な社会人と出会うことで、奨学生に社会的なスキルを身につけてもらう
こちらは奨学生が1年生の間に実施しました。
3)奨学金の増額(上限を月額3万円から6万円に)
こうした、資金援助だけにとどまらない支援を開始した背景には、リタイアされる子どもの多くが、その背景として抱えていた孤立感を少しでも解消したいという想いがありました。
結果として、実施前と比べると奨学生の中退率は低下しました。子どもたちはこうしたプログラムへ最後まで参加をしてくれていたため、Living in Peaceもわずかながらでも居場所の一つとなれたのかなと思います。
2019年以降に採用した学生は接していてレジリエンスの強さが感じられたので、施策だけではなく奨学生自身の自力によるものもあったと思います。特に、新型コロナウイルスの感染拡大で孤立しないかが不安でしたが、同じ学科の友人、部活動/サークル、アルバイトなど自分の居場所を見つけて過ごせたようでした。
■2025年卒業の奨学生からメッセージ
私が大学生活の中で最も力を入れて取り組んだことは、栄養士としての実習です。4年間、沢山の実習を通じて、座学で学んだ知識を実際の現場に応用し、栄養の重要性を深く実感することができました。特に、大量調理実習では時間の制約や食材の調整に挑戦しながら、チームの仲間と協力し合い、安心安全でおいしい給食を提供することができました。また食育では、ポスター作成や小学校では紙芝居形式の授業、保育園では遊びを通じた活動を通じて、子どもたちに食の大切さを伝えることができました。これらの貴重な経験を通じて、栄養士として必要なスキルをしっかりと身につけることができました。卒業後は、この経験を活かして、保育園の栄養士として食の大切さを広めていきたいと考えています。
支援してくださった方々、本当にありがとうございました。
<奨学金事業の終了>
2020年度から開始した国の修学支援制度にて社会的養護下の子どもが進学をする場合、給付型奨学金の受給と学費の免除が受けられるようになりました。本制度により、社会的養護下から高等教育へ進学することの経済的なハードルは下がり、進学率は増加しつつあります。(特定非営利活動法人ブリッジフォースマイルの調査では2022年度進学の割合は約4割です。)
これにより、経済的な不平等を解決するといった当初の課題については一定の改善が見込まれると考え、2020年に新規奨学生の募集を終了し、2025年3月に最後の奨学金給付が完了しました。
■奨学生の採用実績
第1期奨学生(2015年度) :採用2名(卒業1名、退学1名)
第2期奨学生(2016年度) :採用2名(他奨学金合格のため辞退1名、退学1名)
第3期奨学生(2017年度) :採用2名(退学2名)
第4期奨学生(2018年度) :該当者なし
第5期奨学生(2019年度) :採用5名(卒業3名、退学2名)
第6期奨学生(2020年度) :採用5名(卒業5名 ※1名は1年休学の上2025年卒業)
修学支援制度により社会的養護の下から進学することへの経済的格差は縮小しました。ただそれでも、進学後は家庭を頼れない方が多く、生活費のためアルバイトが必要です。また、不調やトラブル時に頼れる人がいないことで孤立しやすい環境にもあります。措置延長により制度的には施設に在籍しながら進学することも可能になりましたが、多くの方は進学を機に一人暮らしを始めるため、引き続きソフト面の支援が求められることとなると思います。
これからの事業について
進学は自分のキャリアを築く上での一つの選択肢ですが、児童養護施設に入所している子どものうち、半数以上は被虐待の体験があり、自身の自立に前向きになることへの課題も抱えています。Living in Peaceでは「社会的養護下の子どもが自立に対する前向きな意欲を持ち、行動できる状態」というゴールを達成するために、児童養護施設に暮らす中高生を対象とした自立支援・キャリアセッション事業を行っています。
また、お金の管理は社会的養護下から一人暮らしをはじめる際に多くの方にとって課題となります。Living in Peaceは、「社会的養護下の子どもが、今後の人生に必要なお金の知識を身につけることにより、生まれ育った環境に関わらずもっと自由に生きる」というゴールを達成するために、お金の教育事業を行っています。
すべての子どもが、生まれや育ちのために自らの可能性を諦めなくてよい社会を目指し、今後も取り組みを進めてまいります。
すべての子どもが、生まれや育ちのために自らの可能性を諦めなくてよい社会を目指し、今後も取り組みを進めてまいります。