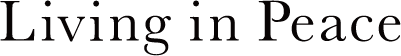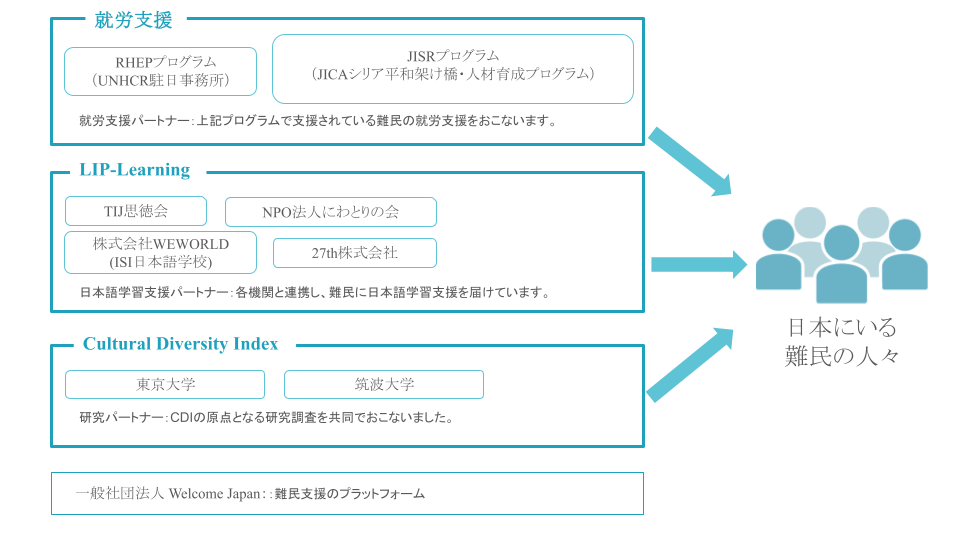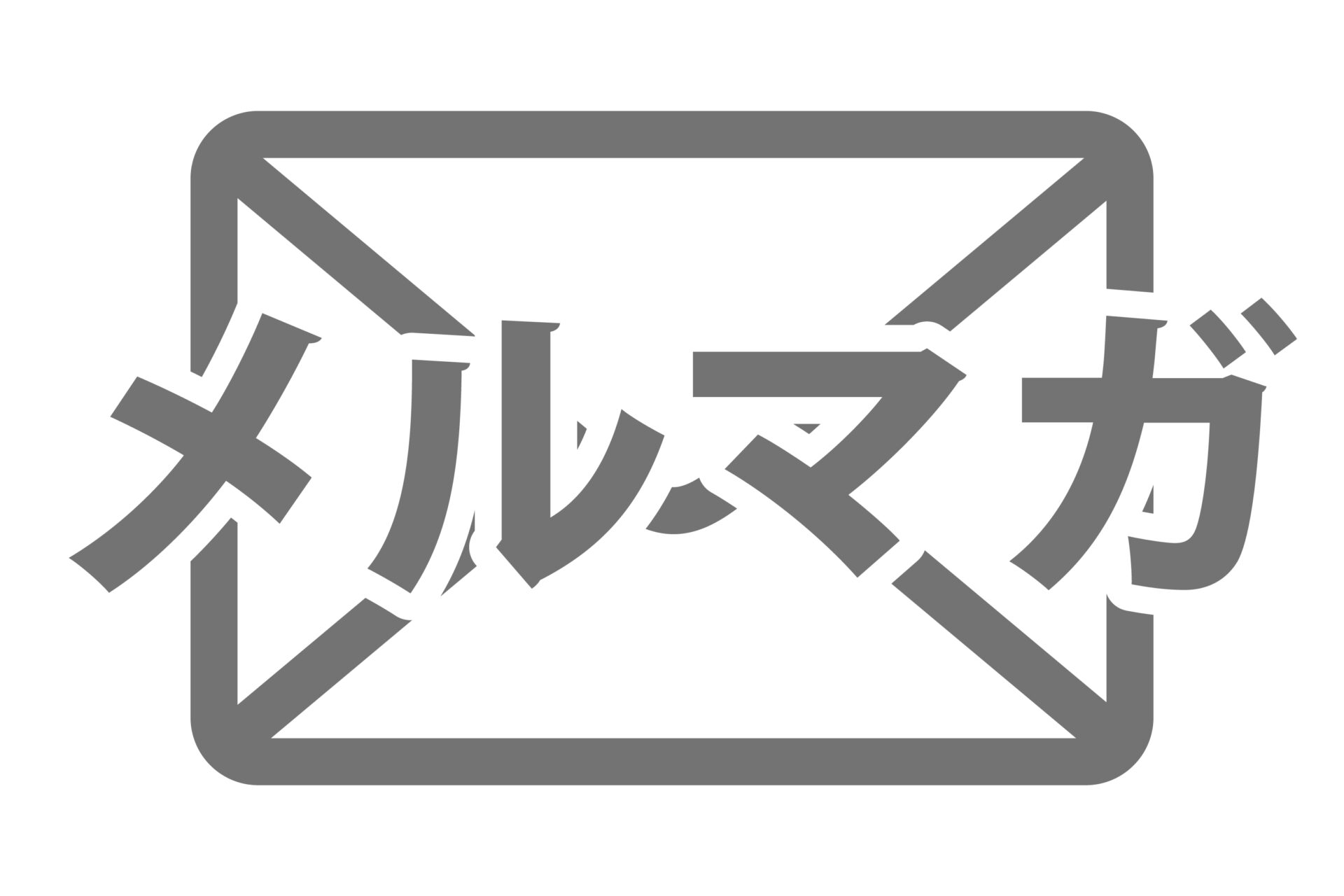わたしはピースをしない。その仕草がどういう意味で、どうしてそれをするのかが、いまだ分からない。カメラを向けられても、周囲がみなそれをしても、「はい、ピース!」と掛け声がかかっても、わたしはピースをしない。
もちろんそれはいかがなものか、という感覚がないわけではない。ピースが完全に習慣化したこの国では、どこでも老若男女がピースをする。やらない方が不自然で、普通でない。必要なのは、せいぜい指を二本開いて前にかかげるという簡単な所作にすぎない。
そうしたことは分かったうえで、なおわたしはピースをしないのは、周囲や社会への抵抗としてではない。そんな抵抗をあえてしなければならない道理などない。ただ、ピースをしたいという思いが湧かないというだけで、だからわたしはピースができない。
ピースをしたいと思えないそんなわたしがピースをしなくてよい状況は、あえて言うなら、ピースをしないという選択が権利として保障されている状況である。
いまやや唐突にも持ち出した「権利」という言葉は、「みずからの利をかなえる力」という意味をそなえた和語である。それは明治初期に「理にかなった正しさ」をあらわす”Right”の訳語として新たに作られ、定着した。
思えば、ピースをしないというのは、「何もしない」ということでは決してない。ピースをしないという選択を、ときにみずからの内外での葛藤を乗り越えてでも、自らのものとして行うということだ。また、ピースをしないということにおいて、私が私であることを(何より自らに)示すこと、そのために己の力を発揮することだ。
とは言うものの、結果、わたしだけ周囲とは違ったことになっているのは、それが周囲との違和を狙っているのではない以上、本意でない。だから、わたしはせめて精一杯の笑顔をする。ピースをする人がその指に込めているだろう思いを、わたしは自らの笑顔に込める。それならできる。
しかし、である。考えてみれば、みんなで写真を撮るときに、求められる表情があるのはどうしてだろう。そもそも、なぜ顔を前に向ける必要があるのか。はたまた、なぜ私たちはいま一緒にいるという事実だけでは満足せず、わざわざ写真を撮ろうとするのか。
こうした思いに伴って生じる「しない」の実現は、「ピースをしない」以上の困難があきらかに伴う。案に相違してその思いが実現しないばかりか、ややもすれば本人は居場所を追われかねない。
「[力士の]隣の人の力はもとより力士よりも弱かるべけれども、弱ければ弱きままにてその腕を用い自分の便利を達して差しつかえなきはずなるに、いわれなく力士のために腕を折らるるは迷惑至極と言うべし。」(福沢諭吉『学問のすすめ』)
多くの人には「一万円札の顔」という、取り換え可能な存在でしかなかかったかもしれない福沢諭吉が、いまから一世紀半前には驚天動地の思想だったはずの「権利」(同書では「権理道義」)について語るなかで、このように書いている箇所をわたしは好む。
一人だけピースをしない。笑顔でない。そっぽを向いている。あるいは、写真からたえず逃げる。それらは変かどうかで言えば、変である。断固として変である。しかし、それでいい。変でいい。いきおいそれらは弱っちくもあろう。しかし、それでいい。「弱きまま」でいい。それこそが「権利」ということばで、その始原に何度でも立ち戻りつつ、私たちが護らねばならないものだと、わたしは思う。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!