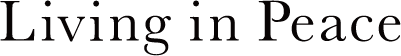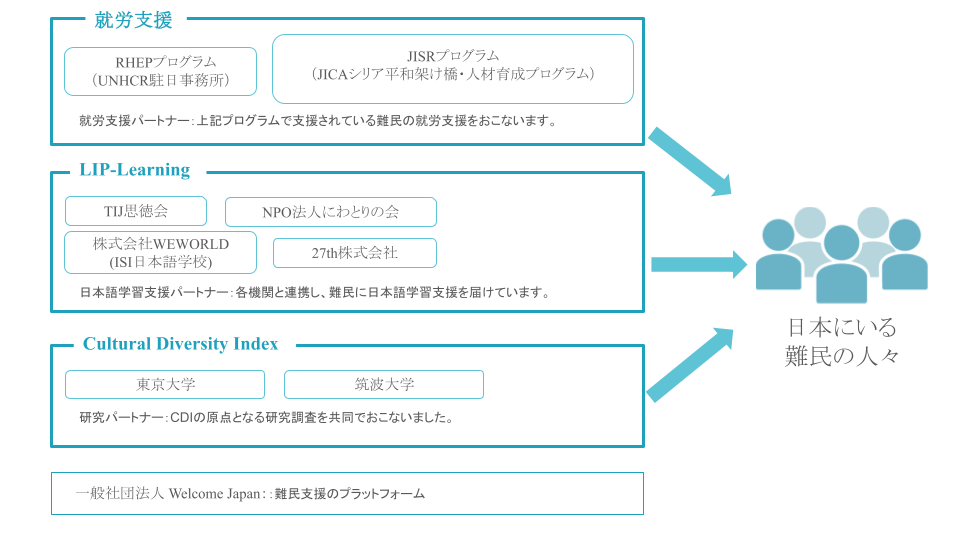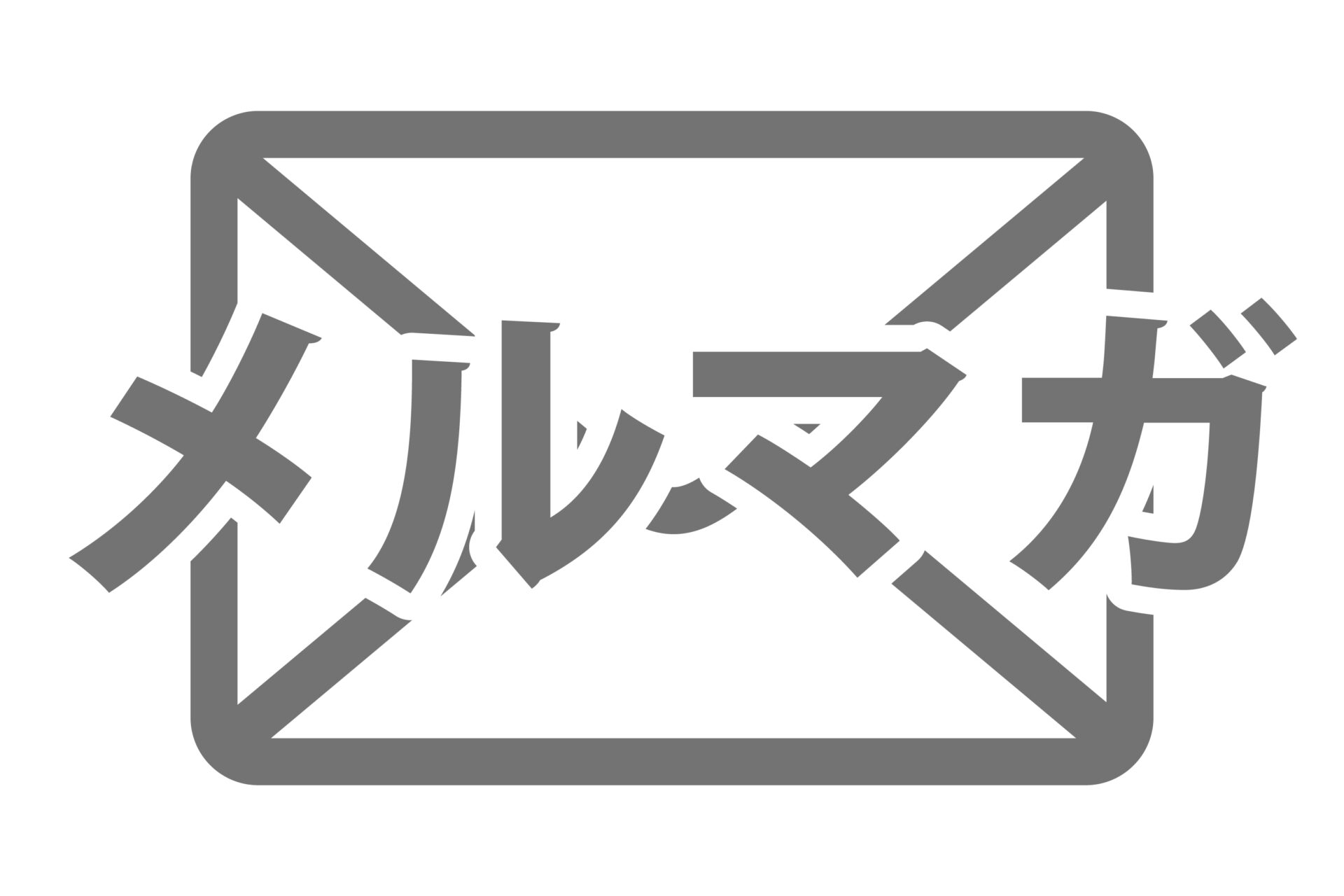夜更けに寝ぼけながら洗いものをしていたら、手から小皿がすべり落ちて嫌な音がした。はっと確かめると無傷だったが、うつろ目で洗いものを続けるうち、ぼやけた視界の奥から口縁が変に欠けたコーヒーカップが現れた。
色かたち、手取り、口当たりのどれもこれ以上なく愛用していた白磁のコーヒーカップだった。あるはずの破片はすでに流されて周囲にない。ゴミ受けをさらって、それらしいものを集め、本体とともに洗い清めた。
一通り洗いものを終えて、そのまま眠る気も失せた目で壊れたものを眺めていると、欠けた口縁から高台に向かって一筋の亀裂もある。それらをきれいに継いだとて、私が気に入ってほんの少し前まで馴染んだものと決定的に変わってしまうのは明らかだった。
ただ、わたし自身も意外だったのは、迂闊に傷つけたことはもちろん(とても)ショックながら、今まではこれ以上なくできあがっていたそのものとそれを愛用する私とが、その決定的な傷を介して、接し、交わり、重なろうとするかのような不思議な感覚を覚えたことだった。
それ自体、ない方が良いことでありながら、ない方が良いことが起きたことで、私とそのものとの関係は、それ以前よりも固有の色を帯びて、変容した。気づけば私は、より近いところでそれを感じていた。
*
以上はコーヒーカップの話に過ぎないが、私が受け取ったことの射程は多少なりとも広いように思う。
まず、何であれ在るものは傷ついたように見えて、ひとまずはそのようなものとして在り続ける。傷つき、何かが欠けたことで元の完全性が失われたように見えつつ、だがそのものは在る。
だから傷つきかどうかは、それを傷つきと認めるかどうかである。しかしそれを傷つきと見なして触れようとするとき、何かをつくろいケアする行為がそこに生まれる。
そしてまた、傷のありかを焦点として「見る」から「触れる」へと転じるときに、私たちもまた受傷する。たとえば包丁で手を切った人の傷口を認め、そこに触れようとするならば、私たちの手もまた、その傷口を介して包丁の刃に触れ、受傷する。
もちろんそれは現実のからだに生じることではない。何による傷かが知れないものも時にあろう。それでもケアとは、相手の傷に関わって、傷に触れることで傷ついた自身をも、ともにケアすることを含意していると私は思う。
それゆえ私たちは、ケアにおいて自身もまた傷つき、壊れうるものとして相手のものである傷を分かち持ち、そこからの方途をともに探るのである。
そうであれば触れることから始まるケアは、私たちがみな壊れうるものであるという可傷性に立ち戻りつつ、傷と見えるものを分かち合うなかで、ともに在り続けることに向けて、関係をあらたに織り直すものになるはずである。
そして私たちは、おそらくそのようなことを通じてのみ、存在するものそれぞれがみな唯一であるという、ある意味で当たり前すぎることに気づくのではなかろうか。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!