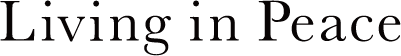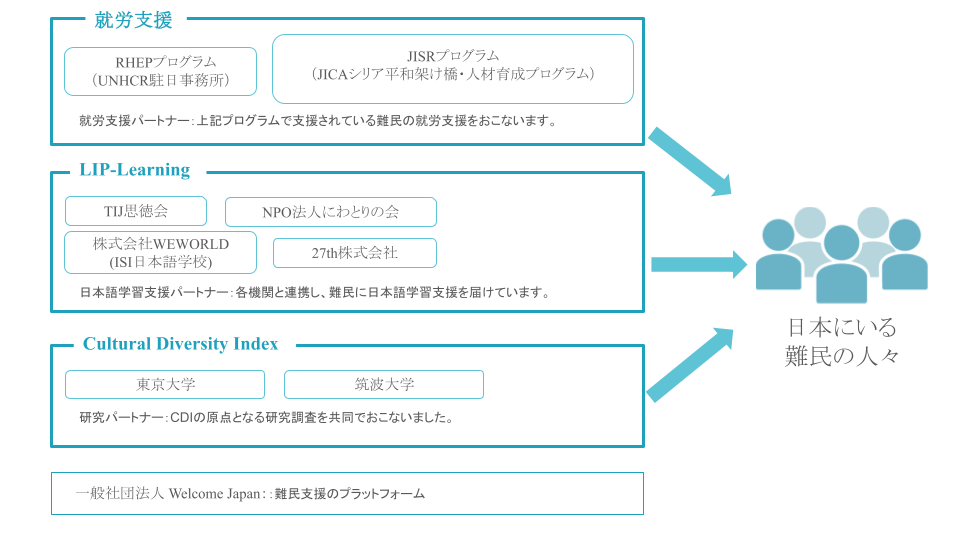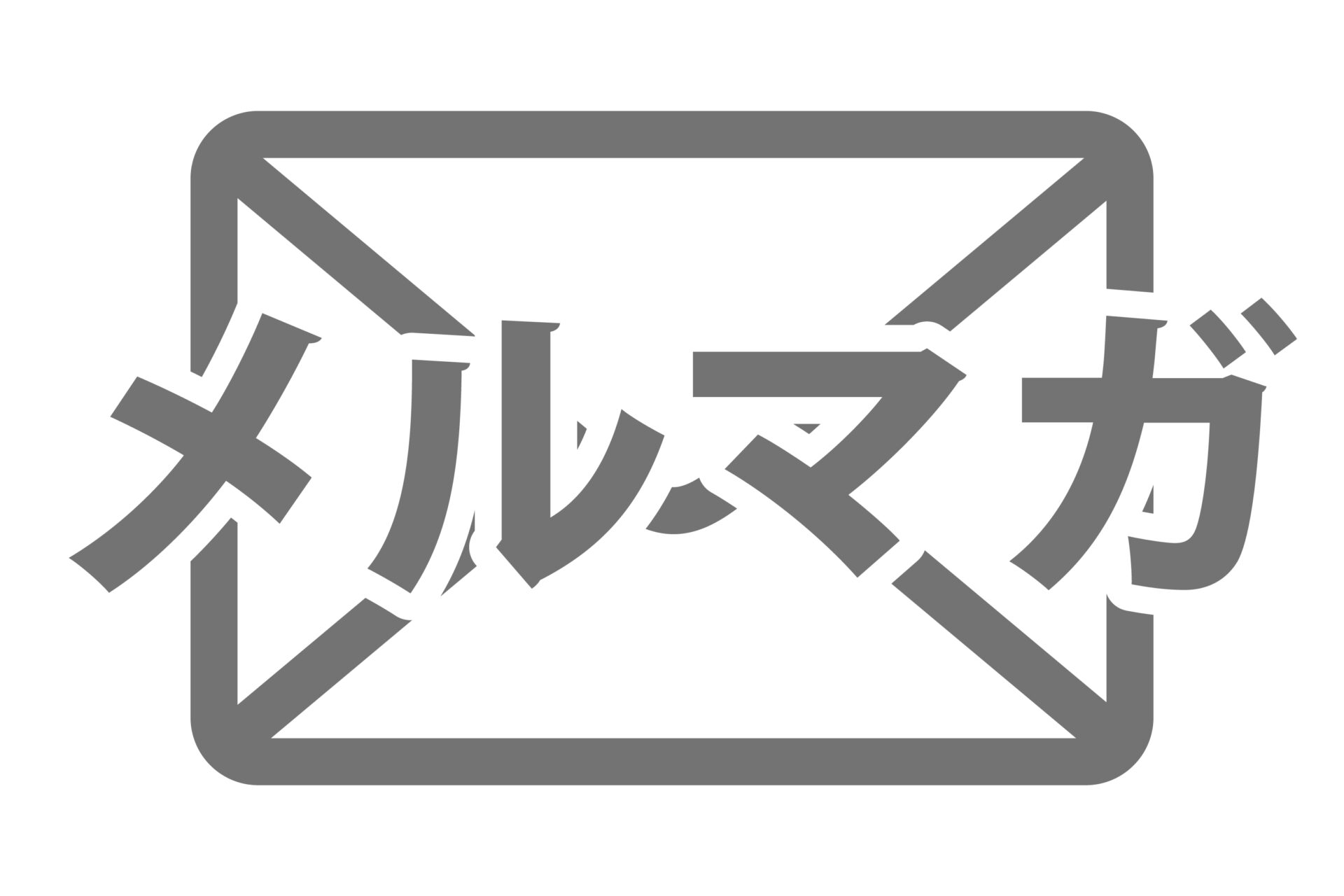「私は半分逃げたのだと思う。しかし、少し跳んだのだとも思う。」
ひとりの老境にさしかかった陶芸家が、豊かな作品をひとつずつ収めた作品集の最後に、かつて画家になることを夢見た青春期について、そう記している。
私の場合、芸術家たるに不可欠な彼ほどの謙虚さを持ち合わせていないから、少しものを考えるようになって始まる自身の身勝手な遁走について、「半分」とも「少し」とも形容できない。
しかしその一文は、私が周囲にしたり顔で説明していたほどには意味がよく分かっていたわけではない今にいたる蛇行の連続が「遁走」だったこと、精一杯の跳躍であったように精一杯の逃避行でもあったことを、やさしく教えてくれた。
20歳を少し過ぎて、よく知りもしない哲学に一方的に思いを寄せたのは、日に日に速まる流れに抵抗するすべを求めた以上のものでなかったと、いまでは思う。言葉にならないものを抱えながら、強い力に押し流されていくのは嫌だったというか、何か恐ろしかった。
たとえば、在るものが無くなってしまうのはどうしてなのだろう。在るものが、それ自体のうちに在ることの根拠をうちに宿していると言えるなら、なぜそれが在らなくなることが可能なのだろうか。
その当時、父母や犬と暮らしていて、夜みなが寝静まった時間にひとり部屋で起きていると、どこからともなく寝息が聞こえてくるような気がして、それぞれの存在の確かさが感じられた。しかしその瞬間にもまた時が過ぎゆくなら、その確かさのどこかに、来たるべき別れが胚胎されているというのだろうか。在ることのどこに非在の兆候があるというのか。
生きて在るものは、いつか消えて無くなるという、その常識的理解への無抵抗な服従を拒みたい動機と実感とが、わたしにはあった。いかにそれが何者でもない私の、取り立てて語られるべきものもない日常における泡沫の如きものだったとしても。いや、所詮そんなものでしかないからこそ、私と、私の日常と、私の日常における一回性のまじわりの意味とを語る者がいるとしたら、それは私でしかあり得なかった。
結果、その頃の私が論文の作法も知ろうとせず書いたものは、「こんなのは哲学でもなんでもない」と見事に無価値かつ恥知らずの烙印を押されて終わった。
今でも私は、どこまでも自分の思ったことを言葉にしているだけの恥知らずに過ぎない。そしていまや(苦言を呈してくださった先生方には申し訳ないながら)それでよいと思ってしまっている。
かつて児童養護施設職員の方が私に、施設職員の専門性は何もない日常をいかに意義深く送れるかにあると教えてくださったように、何もないように見える日常に掬うべきものを見つけようとする養育者の目に見守られ、私たちは一人ひとり他と異なるものを育む。
日常に意味を与えようとする温かく粘り強い養育者の目は、与えられた意味が最初からそこにあったかのごとく見えるなかで、もしかしたら養育者当人すらその存在に気づかないことも、あるかもしれない。
そうであればなおさら、日常とは意味があるゆえに語られるものではない。一見して意味がないように見えようがそれが語られていくなかで、日常が、そこに生きるものたちが、固有の彩りをもって立ち現われてくるのだろう。そして、少なくとも私にとっては、哲学もまたそのためのものでしかありえない。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!