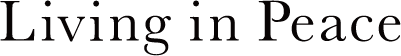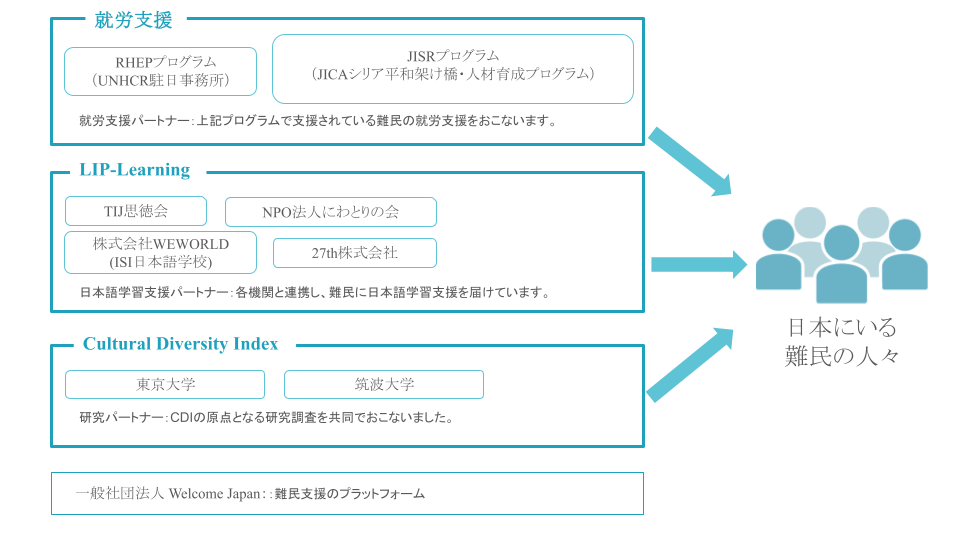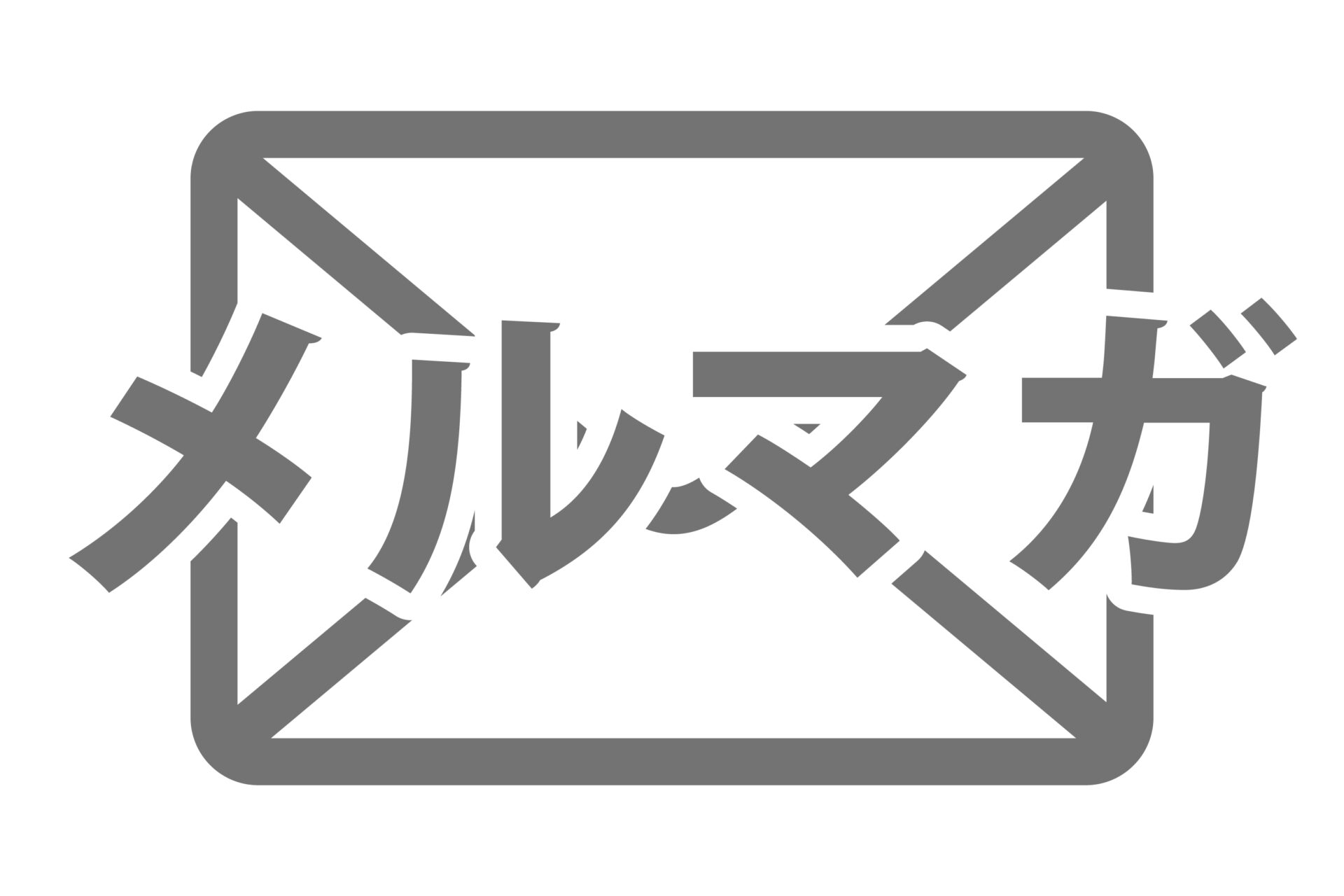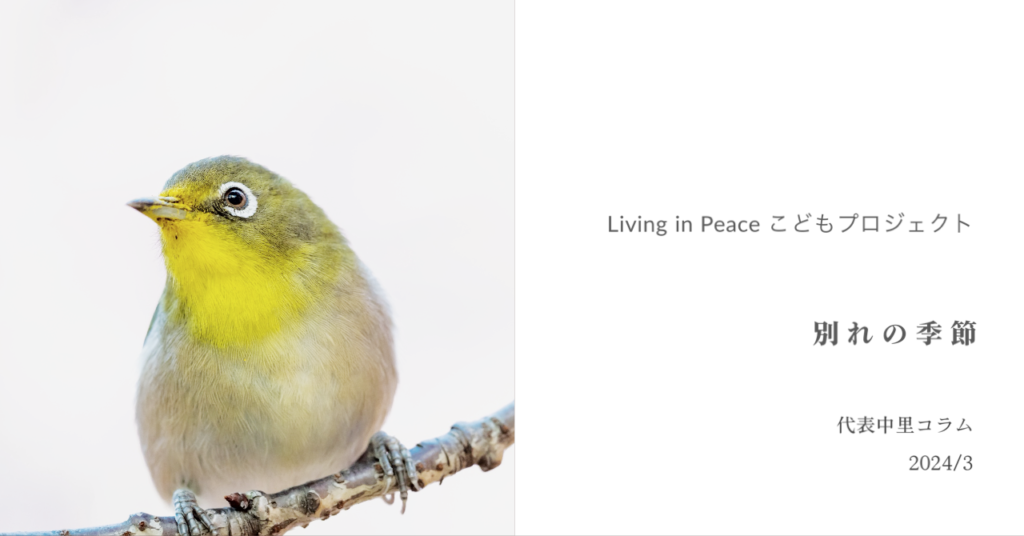
三月は暦のうえは春でも、部屋のなかはまだまだ冷える。私は万年冷え性で、夏場でも手足があまりに冷たいのでよく人に驚かれるが、寒いとことに足先が芯から冷えて堪える。
とくに日中は、寒さをアルコールでごまかすわけにもいかず、じっと辛抱するほかない。しかし数日前、どうしようもなくなって、ふと窓辺を見やると、陽の光が意外にやわらかく、梢の間から手のなかに隠れそうなメジロがその翠色を宝石のように輝かせていた。少し間をおいて、ピーピー、チーチーと澄んだ声が聴こえてくる。こんなときの心の華やぎは、とても言葉にはできない。
こんなことに限らず、大なり小なり言葉にできないと感じることはしばしばある。ただ、言葉にできなくとも言葉にしてみることで生まれるものがある。
世界のまったき姿を写し取ること、それが言語の至上の目的ではないはずだ。何千年たっても埒の明かない哲学のアポリアは、言葉や言語を世界を認識する鏡のごとく考えるところから生じるように思うが、人間の知性は言語使用や言語処理の巧みさであるかのような能力観は一般にも共有されている。
私たちの言葉は、声であれ文字であれ、誰かに聞かれ、見られするように、他者に向かって発せられる。他者がいるからこそ、言葉が生まれる。聞かれ、見られしたときに何が伝わるのか、あるいはそもそも何かが伝わりうるのか分からないことすらある。それでも、私たちはコミュニケーションの可能性に向かって、言葉を使うことをやめない。いや、やめられない。
赤ちゃん、動植物、あるいは死者や物にも、私たちは言葉をかけてしまう。言語を解さないものに向かって、言葉を使うことをやめられない。それは、言葉を使わなければ呼びかけられないからで、伝わると思っているからではないだろう。メジロのさえずりもまたそうであるように、言語使用は私たちの性(さが)である。「特権」と言えば聞こえがよいが、つまりは私たち固有の制約である。
ただ、言語を使うことが呼びかけることの全てなのではない。それを思い出させてくれるのが、言語を解さないものたちとのやり取りである。いまこの瞬間をいきいきと生きてみせる彼らは、言語なしに私たちとの関係を切り開いてみせる。
言語はコミュニケーションの全てではない。だけれど、私たちが言語を使うことから下りるのは至難である。ならば、逆説的かもしれないが、たとえば言葉にならないものを言葉にしてみるその瞬間は、私たちが他者と共にあることのあかしである。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!