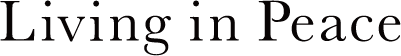昨年、『インディペンデントリビング』という、大阪を舞台に、障害者の自立生活運動を追ったドキュメンタリー映画が公開されました(田中悠輝監督)。原一男監督の『さようならCP』からほぼ半世紀、障害を抱える人のリアルを写した映像作品として、つぎの半世紀を見据える傑作だと思い、感銘を受けました。
劇中、印象深い場面があります。脊椎損傷で四肢が自由に動かない渕上賢治さんが、車いすのうえで仰向けになる格好で介助者にタバコを吸わせてもらうやり取りが、冒頭から繰り返し映し出されるのです。
タバコをさっと差し出し、火をつける介助者に、タバコを乞い「うまいなあ」と呟く渕上さん。その光景を見慣れぬ人には、さながら任侠の世界。つい言いたくもなるでしょう。「越権だ!」と。もっとすまなそうにお願いすべきではないか。そもそも彼はタバコを諦めるべきではなかったか。
しかし、その問いかけを差し戻してみます。なぜすまなそうにお願いすべきなのか。なぜタバコを諦めなくてはならないのか。
渕上さんは自分の力を誇示するためにタバコを吸わせてもらっているわけではありません。タバコを吸いたいけれど、一人で吸うことが物理的に困難であるために他の人の手を借りており、また正当にその貸し手を見つけているのです。構図の単純化は、えてして背景的なものを隠してしまいます。
そしてもう一つ、何かの助けを得ようとするとき、何かを失わずしてそれを得るべきでないという発想も、われわれには根強いものです。たとえば、生活保護を利用する世帯へのバッシング(「国からもらっているお金でそんなことして」等)、あるいは生活保護制度じたいが、実現より諦めを助長する、そのような思考に支えられてはいないでしょうか。
とはいえ私が言葉を重ねるより、スクリーンに映し出される人々の「笑顔」、「笑顔」が何よりの答えです。介助者はもちろん、日々さまざまな苦労をされているはずの障害者の方々のあの笑顔こそが、そこで起きていることがあるべき姿だと雄弁に物語っています。
ひとつひとつの諦めを笑顔に変えていく。そんな素朴な営みに、私たちが歩むべき権利擁護があるのだと、あらためて感じ入った次第です。