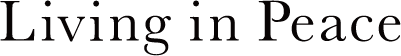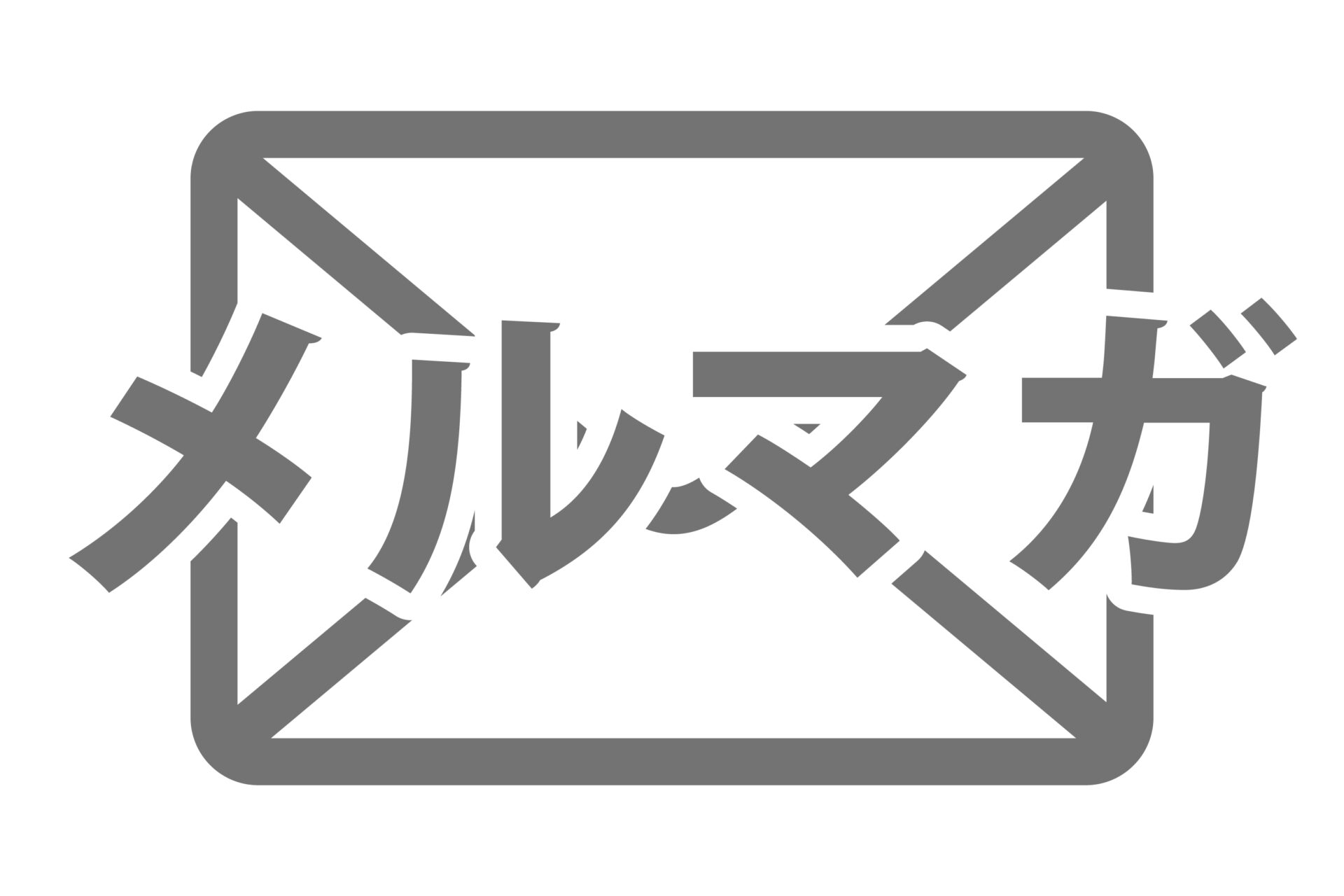一年がまるごと「コロナ」に染まって過ぎ、この四月、新年度を迎えました。
本来「始まり」とは、とくに子どもにとっては晴れがましいはずのもの。それが今年はいつにない陰りを帯びているのではないでしょうか。
もちろんその一部は致し方ないものです。しかし、わたしはその陰りのかなりの部分を子どもを取り巻くわれわれが作り出している気がしてなりません。
端的に言うと、大人たち(そして、社会)は子どもの信頼をこの一年でどんどん失っていると感じます。
「反面教師」という言葉があります。けれど、反面教師は「教師」ではありません。
「こうはなりたくはない」と思う経験をいくら重ねても、「こうなりたい」という想いがそこから出てくることは決してありません。
反面教師は、その他無数にある選択のなかで、目指すべき先を教えてくれないからです。
「こうなりたくはない」と思っていたのに、気付いたらそうなっているような自分に気付き、せいぜい自己嫌悪を募らせるのが関の山です。
子どもを迎え入れるわれわれのほとんど唯一と言っていい責任とは、子どもを護り育てることではなく、おのれの人生を等シン大で生き、真摯にその生き様を見せることではないでしょうか(「シン」は「身」かつ「心」)。
自分のそう生きるしかない、文字通り「懸命の」一個の生を子どもに見せることではないでしょうか。
そしてそれは、敬意を持って子どもを社会に迎えるということでもあります。
自ら望んで生まれてきた子どもは一人もいません。こういう当たり前すぎることを、われわれは都合よく忘れ、「年長者を敬え」「周囲に感謝を」などと言いますが、まったくの論外でしょう。
むしろ、社会こそが最上級の感謝で生まれてきてくれた子どもを迎えるべきなのです。それを形で示すべきなのです。
昨年2020年は、小中高生の自殺数が過去の統計上で最多の499人に上りました。生まれてもらった子どもたちが、「もうこんな人生はイヤだ」と自ら命を絶っているとは不条理の極みです。
今月早々、「こども庁」創設に向けた政府の動きが報じられました。
この望ましい展開を骨抜きにするかどうかは、結局われわれにかかっています。
子どもと日常を共にする私たちが、こどもを中心にすえるまなざしにおいて、一丸となれるかにかかっているのです。