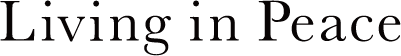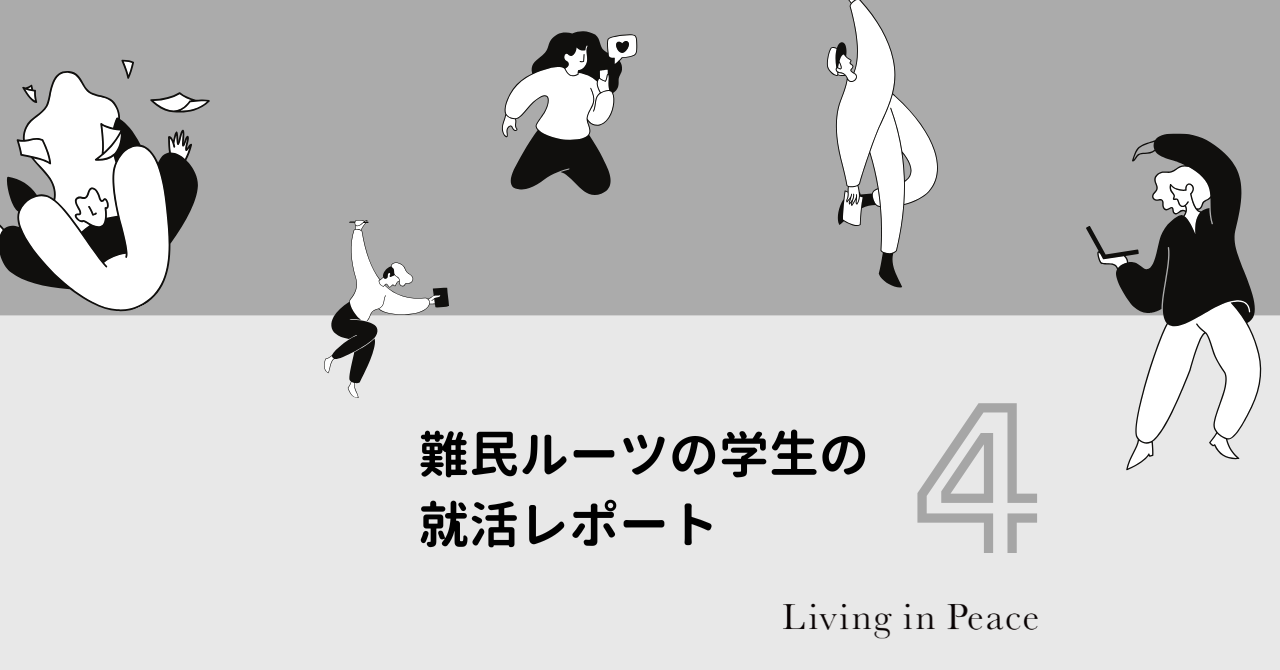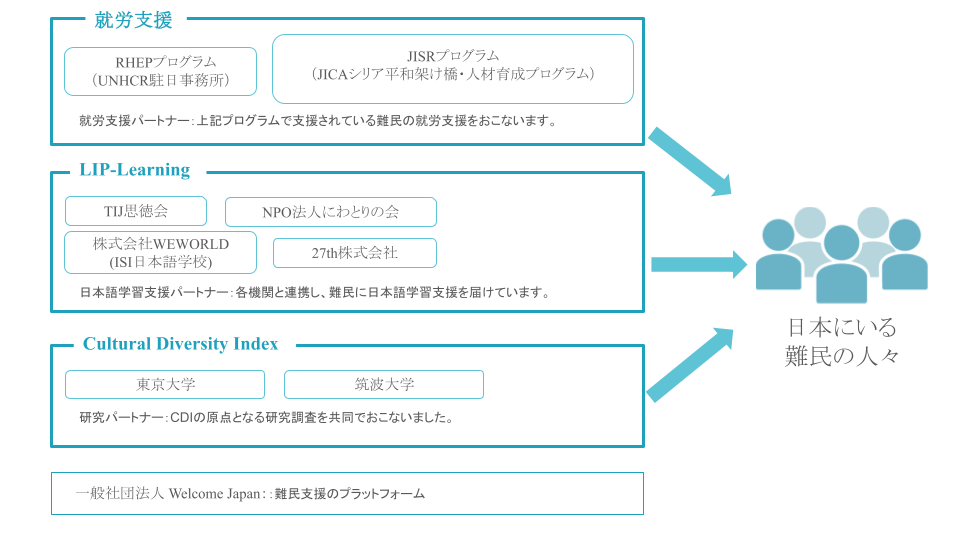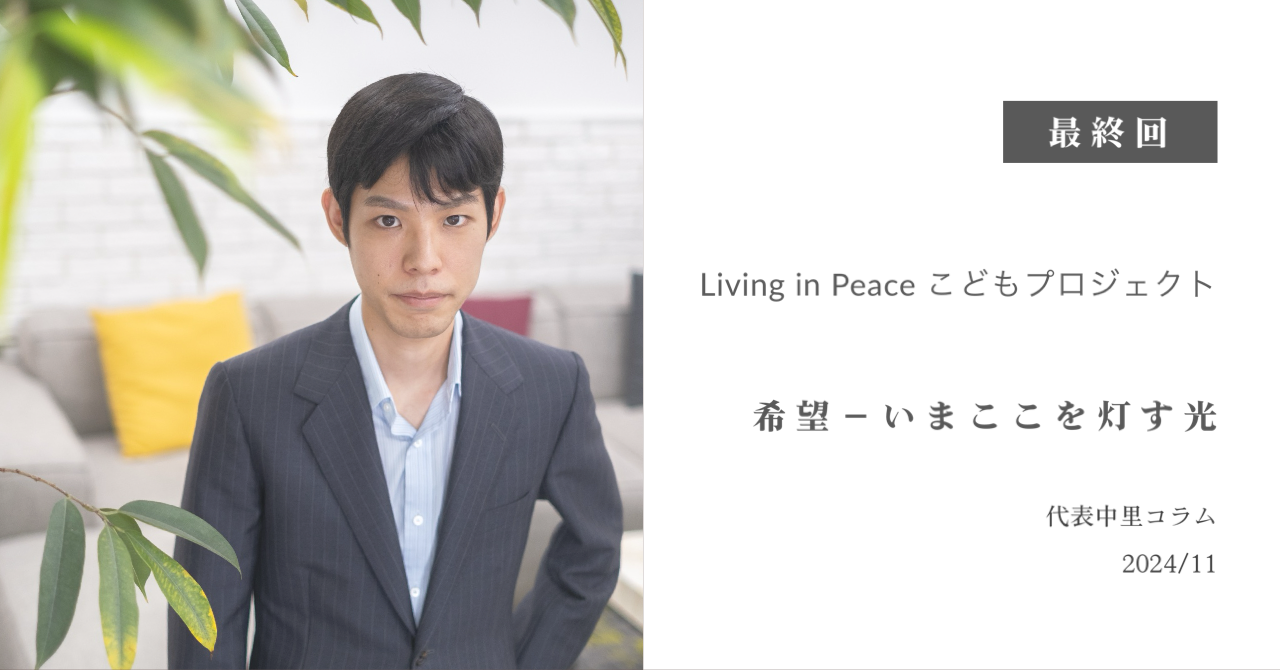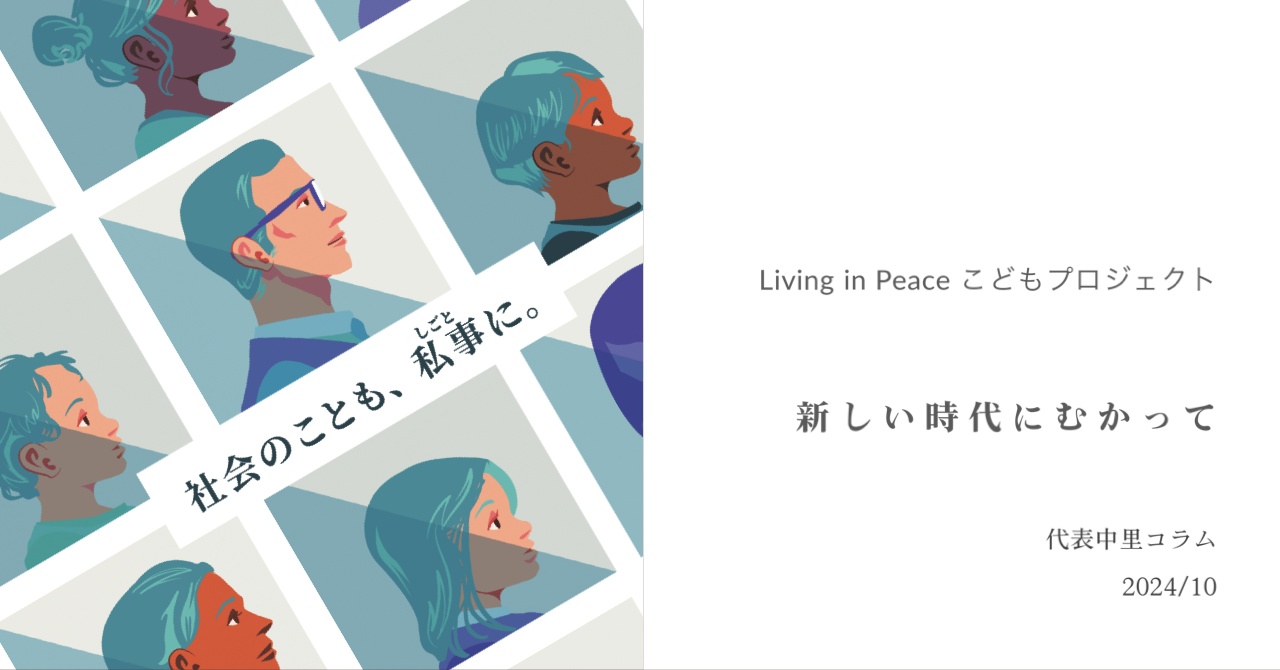Living in Peaceは2018年より、創設者・慎泰俊の後を引き継いだ中里晋三と龔軼群の2名が共同で代表理事を務めてきましたが、今後は両名がその役職を退任し、新たな理事体制で団体を運営していくこととなります(中里はすでに2024年10月31日付けで退任)。
Living in Peaceは2007年の創設以来、「すべての人に、チャンスを。」をビジョンにかかげ、理事を含むすべてのメンバーが本業を別に持つ、無給パートタイムのプロボノとして活動しています。
それは、真に平等な機会のある社会とは、その実現を誰かに委ねることなく、私たちが互いの力と時間を持ち寄って行動することで初めて実現されると信じるからです。
また、すべてのメンバーが対等であるという理念に基づき、オープンかつフラットな組織運営を続けてきました。
Living in Peaceは「社会のことも、私事(しごと)に。」をモットーに、すべての人に開かれた場であろうとしています。安定した運営のもと理念やノウハウなどを適切に受け継いでいくことで、社会により広く、大きなインパクトをもたらす活動となることを目指します。
退任後はメンバーとして活動を継続していく中里と龔が、代表理事としての6年間を振り返るとともに、退任にあたっての想いと、これからのLiving in Peaceへの期待を語ります。
※ 本記事は2025年2月に発刊されたLiving in Peaceの『アニュアルレポート2024』からの抜粋記事です。アニュアルレポートはHPより全文をお読みいただけます。
専門性と個性の違いを共有し、強みに変える
ーー代表理事として、これまでどんなことを意識して活動してきましたか?
中里 私は代表理事に就任するまでメンバーや理事として6年ほど活動しました。それまでどこにいても何となく居心地の悪さを感じていた私は、Living in Peaceがあったことで救われたという思いがありました。代表理事となるにあたって、自分を受け止めてくれたこの団体のかけがえのなさを組織の中できちんと守り受け継いでいくことで、団体への恩返しをしたいという気持ちでした。代表としては、自分自身の興味関心は一方でありつつ、他方で今いるメンバーがどのような景色を見ているか、その中で課題にどうアプローチしようとしているか、それによってどんなインパクトが出せるのかをより考えるようになり、Living in Peaceの可能性をより広げていくことを意識してきたと思います。
龔 私は就任当時はまだ本業でもスタッフレベルでしたし、組織を率いた経験もなく、自分に務まるのだろうかという不安もありましたが、1人ではないということもあり、チャレンジしてみようと思いました。ちょうどマイクロファイナンスプロジェクトでミャンマーでのファンドをスタートさせたり、難民プロジェクトを新たに立ち上げたりと、自分の手がけたものが形になるという手応えを感じ始めた頃でもありました。代表として、団体の取り組みを組織の外にどんな表現で伝えるか、活動の過程で連携・交流するステークホルダーの方々に対してどういう姿勢で臨むのか、私たちが目指す姿をどう言語化するかを考えることに注力してきました。フラットな組織とはいえ、やはり代表は自分の言動が団体の信頼性やプレゼンスに影響する重大な責務だと感じました。
中里 そうですね。私の場合はCode of Conduct(メンバーに求められる行動基準)の存在をいっそう意識するようになりました。もちろんそれまでも心がけてはいましたが、代表理事として団体内外にそれを体現する存在になるのだということは重く受け取めるようになりましたね。

大学院生だった2012年に参画し、こどもプロジェクトにおいて幅広く活動。理事、副理事長を経て、2018年4月から2024年10月まで代表理事を務める。本業は哲学・児童福祉を専門とする研究者。
ーー代表を2人で務めるというのは、心強さもある反面、難しさもあったのでは?
龔 確かに、私たちは専門性も違えば、性格や得意不得意も真逆で、意見がぶつかることも多々ありました。私は取り組みの意義や効果を分析しながら有効性の高いものを推進していこうとするタイプ、中里さんはみんなの思いを受け止め、包摂しながら後押ししていくタイプ。ただ、活動を進めていくにはそのどちらもが必要ですから、いいバランスが取れていたのではないかと思います。
中里 意思決定を担う代表であることでそうした違いが表面化しやすくなるという面もありますよね。限られた時間の中でそうした違いを共有しながら強みへと変えていくには、根気よくコミュニケーションを続ける努力が大事です。組織としてはそれこそがむしろ健全なことかもしれません。
龔 本当にそう思います。ぶつかって議論が生まれるからこそブラッシュアップでき、多様性が生まれる。私1人の知識や関心、熱意だけではLiving in Peaceの活動全体を代表することはとてもできなかったし、お互いに補い合い、助け合えたのは心強かったです。
組織を代表する立場だからこそできた経験
ーー代表理事という立場を経験して、どんな学びがありましたか?
中里 メンバーとして活動していてもいろいろな出会いはあるのですが、代表という肩書があったから得られたであろう人とのつながりや経験は本当に貴重なものでした。私の場合は、児童福祉の現場で新しい時代を作っていこうとしている人たちと関わることができ、本業である哲学・児童福祉の研究者としても視野が広がりました。
龔 私もまさに、本業で立ち上げた新しい取り組みにもつながる方々とお会いできたのは、代表としてさまざまな場に出向くことができたからです。また、人を動かすとはどういうことかを学べたのも大きな財産になりましたね。代表理事就任当初は本業でのマネジメント経験がありませんでしたが、Living in Peaceで活動を推進する経験を積んだことで、想いや熱量がなければ人は動かないし、活動は続かないと実感しました。現場を体感してもらい、「やりたい」「楽しい」という気持ちを持ってもらうというマネジメントスタイルが本業でも評価されて、新規事業を任されるようになりました。
中里 私の場合は本業が研究職なので、社会をどうしたらより良くできるかという観点から組織をマネジメントし、他団体・機関との協働を重ねた経験は、Living in Peaceの代表になることがなければ得られなかったものです。あとは、代表として毎月コラムを執筆したのも、よい経験でした。
龔 全部で70回?あれは大変でしたよね。
中里 例えば論文を書くのとはまったく違って、短い文章の中で多くの人にメッセージを読み取ってもらうことの難しさがよくわかりました。でも、組織の代表だから言えること、書けることがあります。私が守りたかったものや理想を言葉にして残せたとしたら、それは本当に得難いことでした。

2015年に入会、マイクロファイナンスプロジェクトで活動するとともに、難民プロジェクトを立ち上げ。理事を1年間務めた後、2018年4月から代表理事。本業は不動産ポータルサイト運営企業の事業責任者。
バトンをパスし、新しいLiving in Peaceへ
ーー代表理事を退任し、1メンバーに戻るという決断の背景を教えてください。
中里 自身のキャリアにおけるタイミングということもあるのですが、退任ということも含めて代表の責務だと以前から考えていました。代表という立場であっても理事やメンバーのみんなと一緒に取り組んでいる意識はかなり強いですが、それでも長く代表を務めていると、自然と組織に自分の色が出てきてしまいます。そうした状態が続くほど、次に続く人たちが組織を担いづらい状況になるという危機感がありました。私の色だけがLiving in Peaceとしての姿ではないはずだし、別の人が代表を引き継ぐたびに異なる色になっていったほうが、取り組みの可能性もより広がるでしょう。組織として成長し続けるためにも、再任はしないほうがよいと決断しました。
龔 私も、代表としての自分の意見の重みが、組織の内外において年々増してきているのを感じています。私が走り続けないと組織が動かないというのは、サステナブルではないですよね。これまでも、いろいろなメンバーが関わって、いろいろな色があって、Living in Peaceの歴史が作られてきました。これからもそうあってほしいと願っています。
そしてなにより、私自身が代表理事を経験して大きく成長できたので、この経験を他の誰かにもしてほしいんです。若いうちにこんな経験ができるのはLiving in Peaceならでは。私が受け取ったバトンを次の人にパスしなければ、という想いがあります。
中里 同感です。また、活動が広がり、組織が大きくなるにつれ、なかなか難しい課題も出てきています。代表が交代するというのは組織にとって大きな変化になりますが、だからこそそれがそうした課題を克服するきっかけになりうると信じています。
龔 そうですね。これを機会に、Living in Peaceとしてどんな社会を目指していきたいのかをあらためて議論し、活動全体の方向性を定める強い軸をしっかり作っていけたら、より確かなインパクトが出せるようになると思います。新しいLiving in Peaceの展開を、期待をもって応援していただけたらうれしいです。
<2024年11月からの理事体制>
代表理事:龔軼群(重任)
理事:木下祐馬(重任)、 湖山勝喜 (重任)、菅山大世紀(新任)、原 好乃(新任)、大橋彩香(新任)、里見春佳(新任 ※2025年2月1日より)