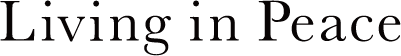「くるしい、くるしい、こんなんは、生まれてこなんだら、よかったんとちがうか、みんながみんな生まれてこなんだら、何もないねんから、何もないねんから——」
川上未映子の『夏物語』第1部、母とふたりで大阪に暮らし、母への葛藤で長らく声を発しなかった12歳の緑子が、最後、母に向かって絞り出すように言った言葉です。物語の第2部では、違う人物から、たとえわずかでも、ほかの人々の幸せをよそにひどい苦しみを生きざるをえない可能性があると分かっていて、なお人を生むのかという問いも発せられます。
いずれも切実な問いです。私たちの日常はそうした問いをむしろ隠すことで平穏さを得ているがゆえにいっそう、それを問わざるをえない状況は切実でしょう。
しかしこのように問いを発することで隠れてしまう真実があることも、一方で忘れていけないことです。それは、私たちは生きようとするまえに生きているという事実、そして、私たちに何かしらの過去があるのと同様、私たちにはここから生み出される未来があるという事実です。
人生はつねに未決であるのに、あたかもそれが定まったかのように感じる。より悪いことに、その定まった中身に応じて生の価値が決まるように感じる。これらは事実ではないという意味で、はっきり幻想と言えるものです。そのことを、まだ何者でもない赤ちゃんが身をもって教えてくれます。
私たちは誰しも生きる力を持っています。それは、前が全く定かでないなかでも歩けば足もとに体を支えてくれる大地を生みだせる魔法の力でしょう。
またその力は、ほかの誰かを生かす力でもあります。私たちの歴史は、過酷な状況においても見事に生きた人々の足跡が散りばめられていますが、ほとんどの場合、それらはともに生き、生かし合った生の姿なのです。
分断は簡単な事実の忘却から始まります。新型コロナウィルス感染をめぐる状況だけでなく、それに端を発して、あるはそれに乗じて、さまざまな問題が重なってくる情況を生きる私たちはとくに、このことを肝に銘じておきたいと思います。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!