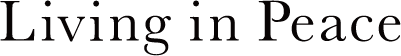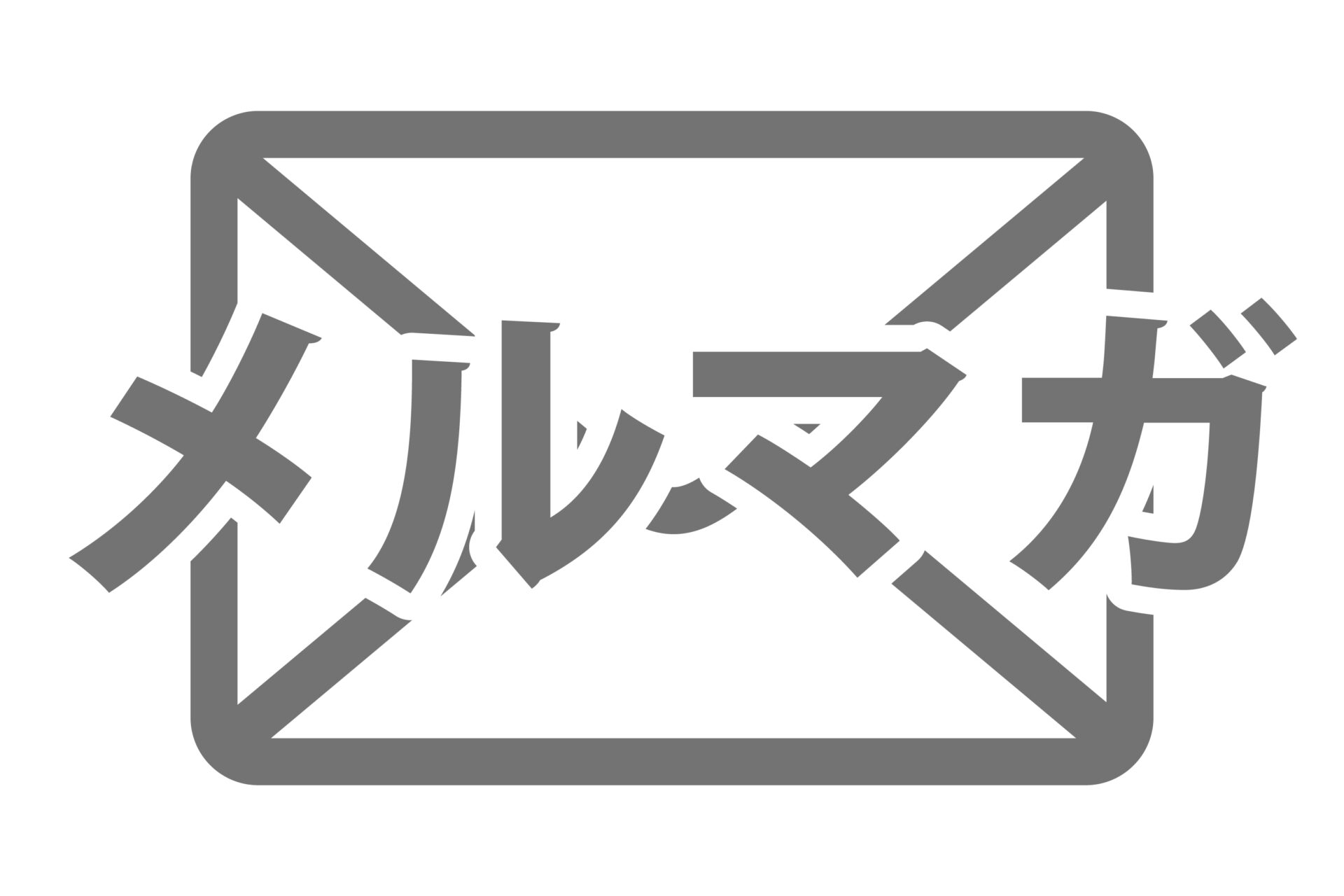11月23日に埼玉県川口市の並木元町公園で、様々な文化的背景を持つ人々と共に暮らす体験するフェスティバル「ともくらフェス」が開催されました。
このフェスのトークイベント「多様性を包摂する社会のつくり方」に、代表理事の龔 軼群が東京芸術劇場の田室寿見子さんと一緒に登壇しましたので、その様子をお伝えします。

田室 寿見子(たむろ すみこ)さんは、2008年に岐阜県の可児市文化創造センターで在住外国人と日本人の交流を目指した多文化共生プロジェクトを立ち上げ、5年に渡って当事者の声からドキュメンタリー演劇を創作されました。その後、2014 年より東京芸術劇場において人材育成・教育普及を担当、多文化社会を拓く演劇ワークショップの開発と人材育成プログラムを展開されています。
田室さんのお話のうち、印象的だったものを2つ紹介いたします。
- 「多文化共生プロジェクトの参加者に、民族紛争が起きたボスニアヘルツェゴビナ出身の男性が戦場での体験を話してくれました。当時、対立しあう3つの民族が同じアパートに住んでいて、夜になるとアパートの住民が同じ部屋に集まって、ろうそくをともす中、ジョークを言いあったそうです。彼は『非常に厳しい時代だったが、同時に強いつながりを感じる幸福な時期でもあった。』と話してくれました。何年もたって、プロジェクトに参加した日本人の方が「あれからずっとボスニアヘルツェゴビナのことを考えています。」とおっしゃってくれ、ずっとあの若者のことを心に留めていてくれたのです。
- 高校生相当の若者を対象にしたワークショップでの起きたことです。事前に関係者から難しいといわれていたのですが、若者が支援を受ける立場から支援をする立場に変わることで劇的な変化が生まれました。自己肯定感が高まることによって大きな変化が生まれるのです。
田室さんの体験をお聞きして、演劇を通じたワークショップには人を変え、異文化理解を後押しし、一人一人違う人々を包摂する強い力があることを感じました。
田室さんの話を受け、龔からはLiving in Peaceの「おでかけリップ」の体験について話をしました。
- Living in Peaceでは、 子どもの体験格差を解消するために、子どもたちに多様な体験・経験を提供する事業として「おでかけリップ」に取り組んでいます。
(おでかけリップについてはこちらをご覧ください。) - 両親がコンゴ出身の5歳の子どもは、参加当初はお母さんから離れようとしませんでした。おそらく、日本人の大人に対する警戒感を持っていたのでしょう。でも、参加を重ねるごとに年配のLIPメンバーに心を開き大きく変化しました。人と人との交流には時間はかかるが大きな変化をもたらします。


最後に田室さんの著書「演劇ワークショップでつながる子ども達 多文化・多言語社会に生きる」の表紙に描かれたビニールテープによる世界地図について説明いただきました。
- 床にビニールテープで世界地図を作り、参加した若者に自分がどこからやってきたのか、今どこにいるのか、これからどこに行きたいのか、実際に世界地図の上を歩いてもらったんです。単に過去のことだけでなく、将来何を望んでいるのかということをお互いに知ることができました。
素晴らしいアイデアなので、そのような活動の可能性も模索してまいります。
参加者のみなさん、田室さん、そしてイベントを企画いただいたともくらフェス実行委員会のみなさんに感謝いたします。