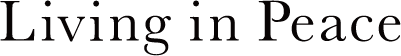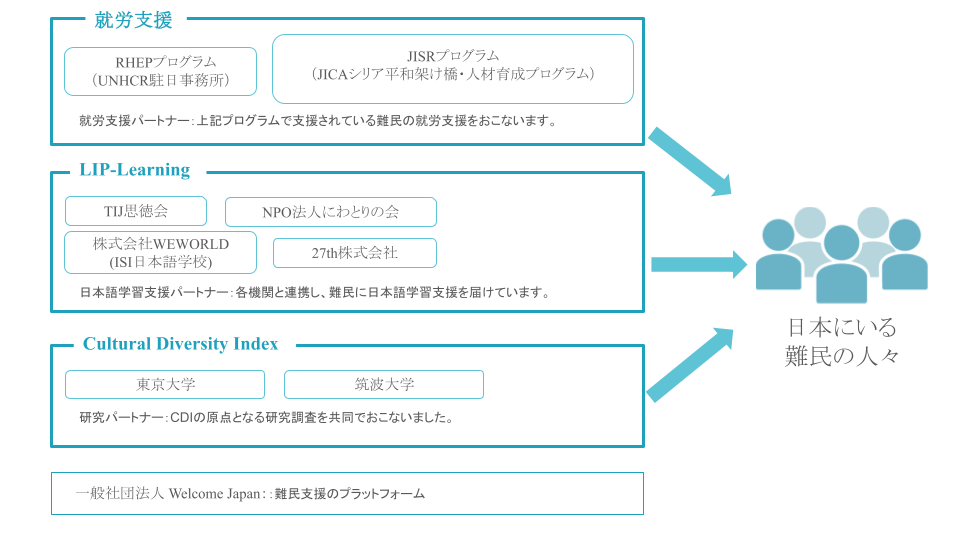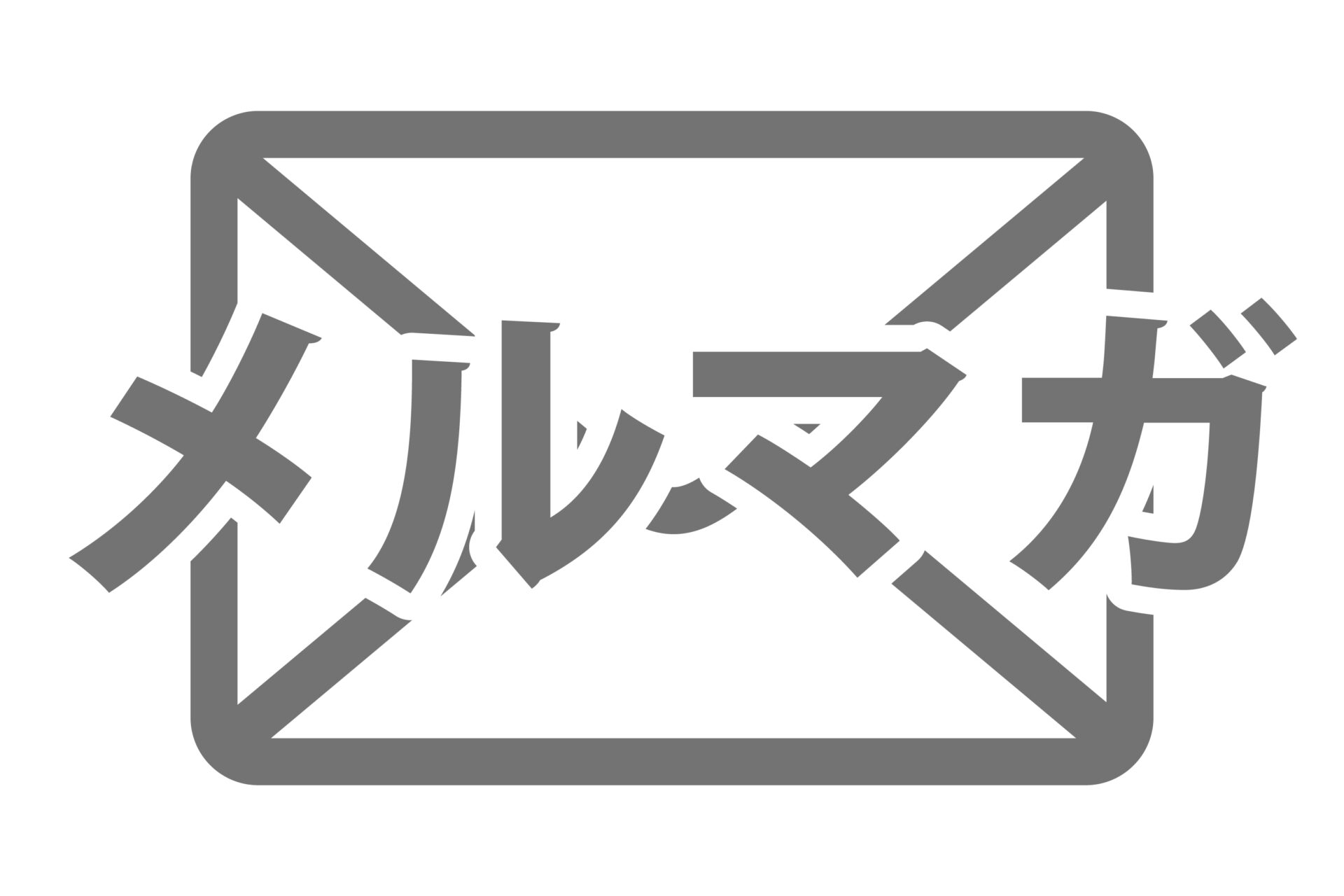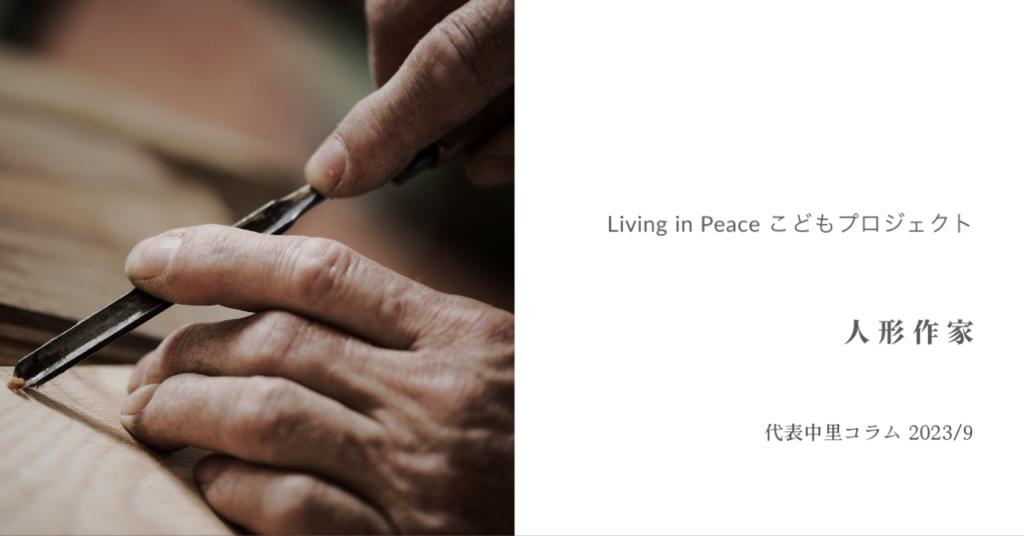
二十歳そこそこの頃、古本屋でたまたま見つけた『人形作家』という薄い本は、表紙をめくるとそのレーベルの堅実さとは不似合いな裸の人形の写真が、10ページほどにわたってカラーで掲載されていた。
表面は生きているかのようであり、しかし同時にスカスカの空洞や骨組みが露呈したその人形の異形。そして、本文に入って「小さいときの僕は、いつもひとりだったという記憶があります。」と始まる作家の半生の聞き語り。それは、古本屋を出てすぐの電柱にもたれて息もつかずに読み終え、数日後にはその人の工房へ無遠慮に押しかけてしまうほど、そのころ私が抱えていたもがきや寄る辺なさを、思わぬところらから照らしてくれた。
見るからに幼さをたくさん引きずった青年を、まず出迎えた工房のお弟子さんたちは当惑していた。とはいえ約束もなく押しかけて痛痒も感じない者は、目の前の人たちが困っているからといって帰るものでない。そうこうしているうちに本人が現れ、私は「人形を見せてほしい」と言った。
何かの最中だったその人は、私を工房の奥へと案内してくれた。そして「ちょうど展示で海外に出していて少ししかないけど」と言いながら、置いてある人形の一つひとつを懇切丁寧に説明してくれた。私が何も知らないことはきっとバレバレだっただろう。優しいまなざしと、語り口だった。
帰りがけに「また来ていい」と言われた気がする。が、そのときの私は目の前の精巧な人形たちにすぐさまに感応できる繊細さを欠いていて、そこから何かが始まることはなかった。私と人形、そしてその人形作家との出会いは、それきりになった。
はた迷惑な話で、不義理もこの上ない。けれど、当時の私にこの出来事は、ほとんど初めて味わったたぐいの心地よい不思議な余韻を残し続けた。それは真に出会うべき出会いだったと思うし、そうした出会いがいかに直感されるかを知った経験が、今に至るまでの私をまっすぐに貫いている。
そして今回、茫々とした記憶を反省して気づいた。木の老精のごときその人形作家は、私が誰であるかについて、ついに何も尋ねなかった。なぜ人形を見たいと思ったのか、ということすら聞かなかった。多分そんなことはどうでも良かったのだろう。私にとっても、それはどうでも良いことだった。今ここにいるという以上の何ものも私は持たなかったし、持ちたいとも願わなかった。だから、とても心地よかった。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!