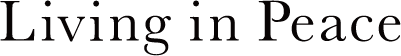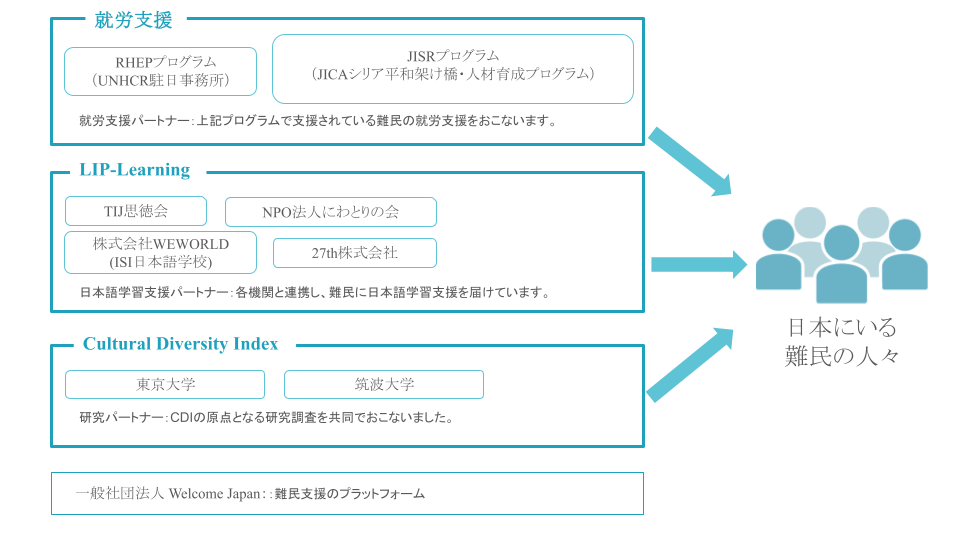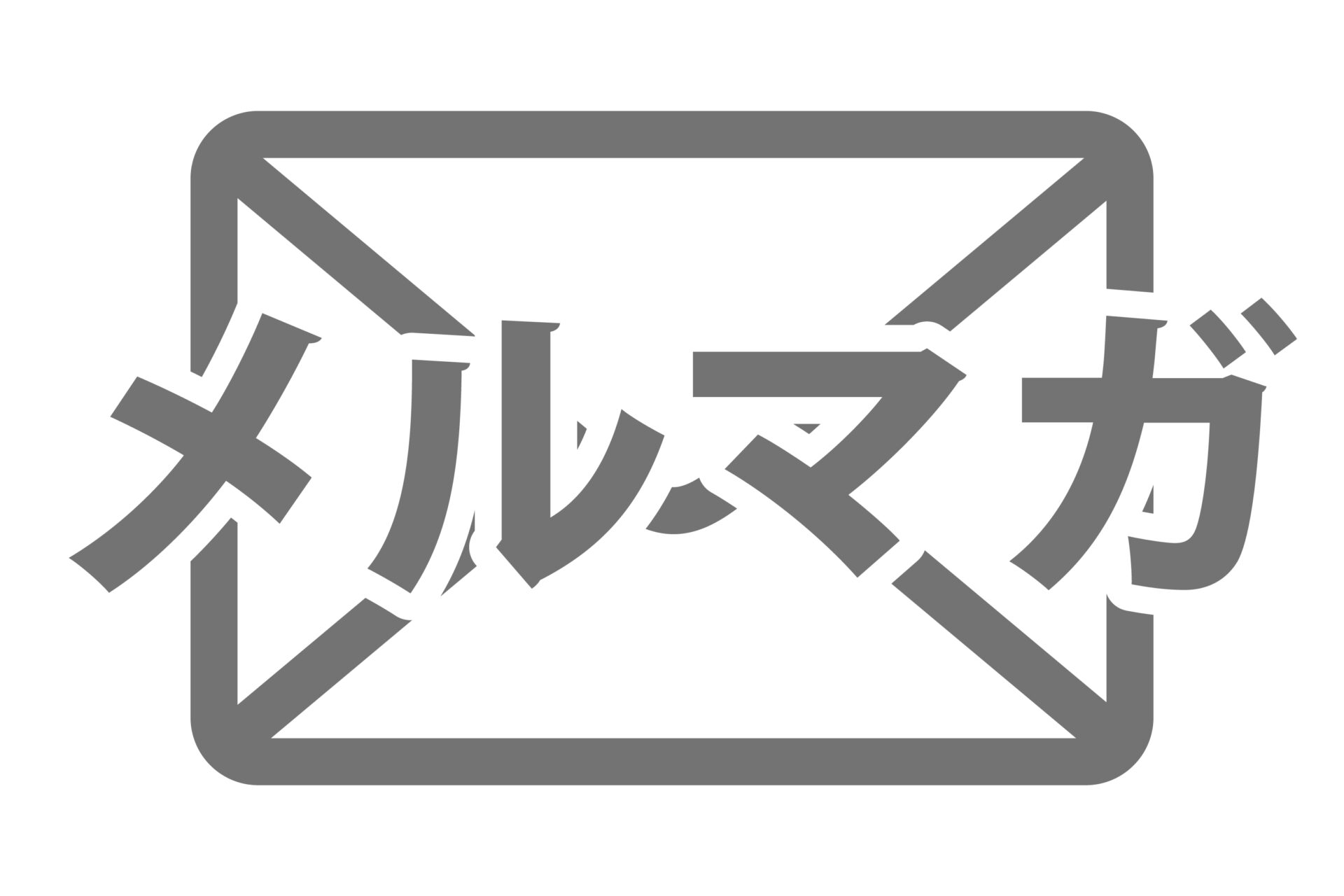ケラケラ、キャッキャ、アハハーッと闊達に、気持ちよい笑い声を上げることが、私たちは気づけばできなくなっています。だからせめてそんな声を聞いていたい、聞かせて欲しいと思って子どもたちの笑顔を求める心は、幸福なエゴイズムと言えましょう。
私の場合、数少ないながら割合に私の期待を裏切らない持ち駒のひとつに(あえてタイトルを付けるとすれば、ですが)「誕生日のおてがみ」という小咄があります。誕生日に祖父母からの手紙を喜んだものの、「あなたは私たちのほこりです」という一文の「ほこり」の意を汲めなかった幼い私は、否定されたと思ってワンワン泣いた、という(記憶の限りは)実際の話です。要点だけ書けばむしろ切なさすら覚える話ですが、子どもたちにはこれが見事にうけるのです。身をよじって笑ってくれます。
その意味では幸福なエピソードとなったこの話の主人公は、その後、大きくなっては「自分よりすごい人に出会ったことがない」と平気でうそぶく輩となり、周囲から顰蹙を買うようになります。本人は本気でそう思っているふしがあったので、なおのこと始末に負えないと思われたでしょう。が、最近、評論家の加藤典洋が高校生向けに話したもののなかに「とにかくこの世にはろくな人間はいない、大した人間はいないと思っていて、[…]タカをくくっていた」とあるのを見つけました。私の青臭い不遜さも、ありがちな典型のひとつだったわけです。
さてその講演録で加藤は、そうした了見がすっかりひっくり返されるほどに決定的な出会いをもたらした人物として鶴見俊輔をあげています。私自身、人が人よりすごくはあり得ないという感覚が沈着しつつありますが、その鶴見が80歳になってから7年のあいだ書き続けた連載をまとめた小著(『思い出袋』)などからは、確かにある種のすごみを感じます。
そのなかに「誇りという言葉」と題された「知っているけれど、わざと使わない言葉がある。」と始まるエッセイがあります。その言葉がアメリカ滞在中に自分に向けられたうれしさを忘れられないでいる一方、その言葉を彼自身はついぞ誰かに使えないでいるという話。使わない、のではなく、使えないのです。なぜ鶴見は「誇り」という言葉を使えなかったのか。「大学とは[…]個人を時代のレヴェルになめす働きを担う機関である」と的確に表現し、日本の教育の貧しさを見抜いている人であるから、もしかするとそれは彼自身のなかで了解済みだったかもしれません。
誰かを誇るには、自分を誇れているのでなければならない。自分を誇るには、人から自分が誇られているのでなければならない。「誇り」という言葉を知る以前から、幾度も、幾度も。それは鶴見俊輔が生まれて100年経っても、私たちが十分に分かったと言うにはまだ遠い、素朴な真実です。
私の不遜さの源泉かもしれないかつての手紙は、鶴見とほぼ同齢の祖父母から送られました。私はいま、それをひとつのほこりとしています。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!