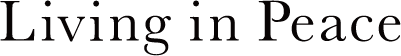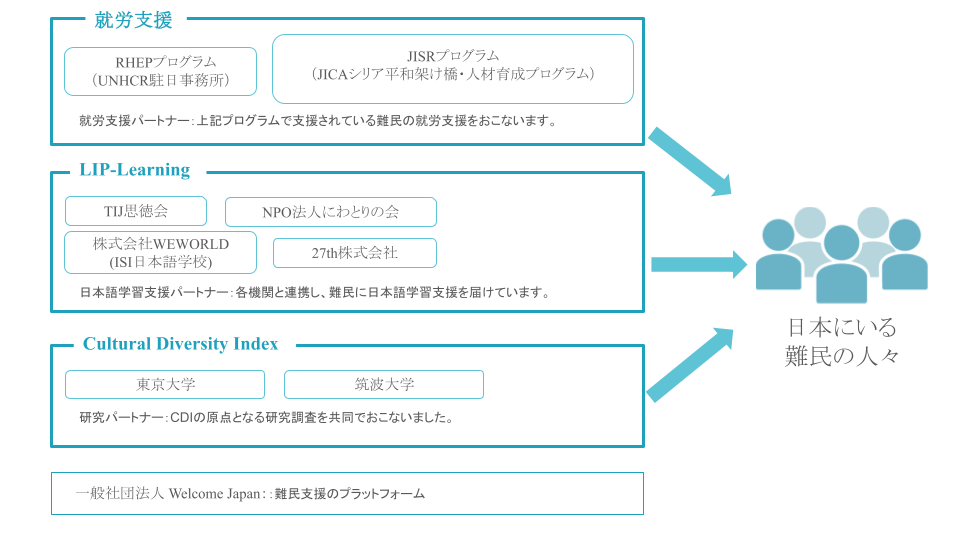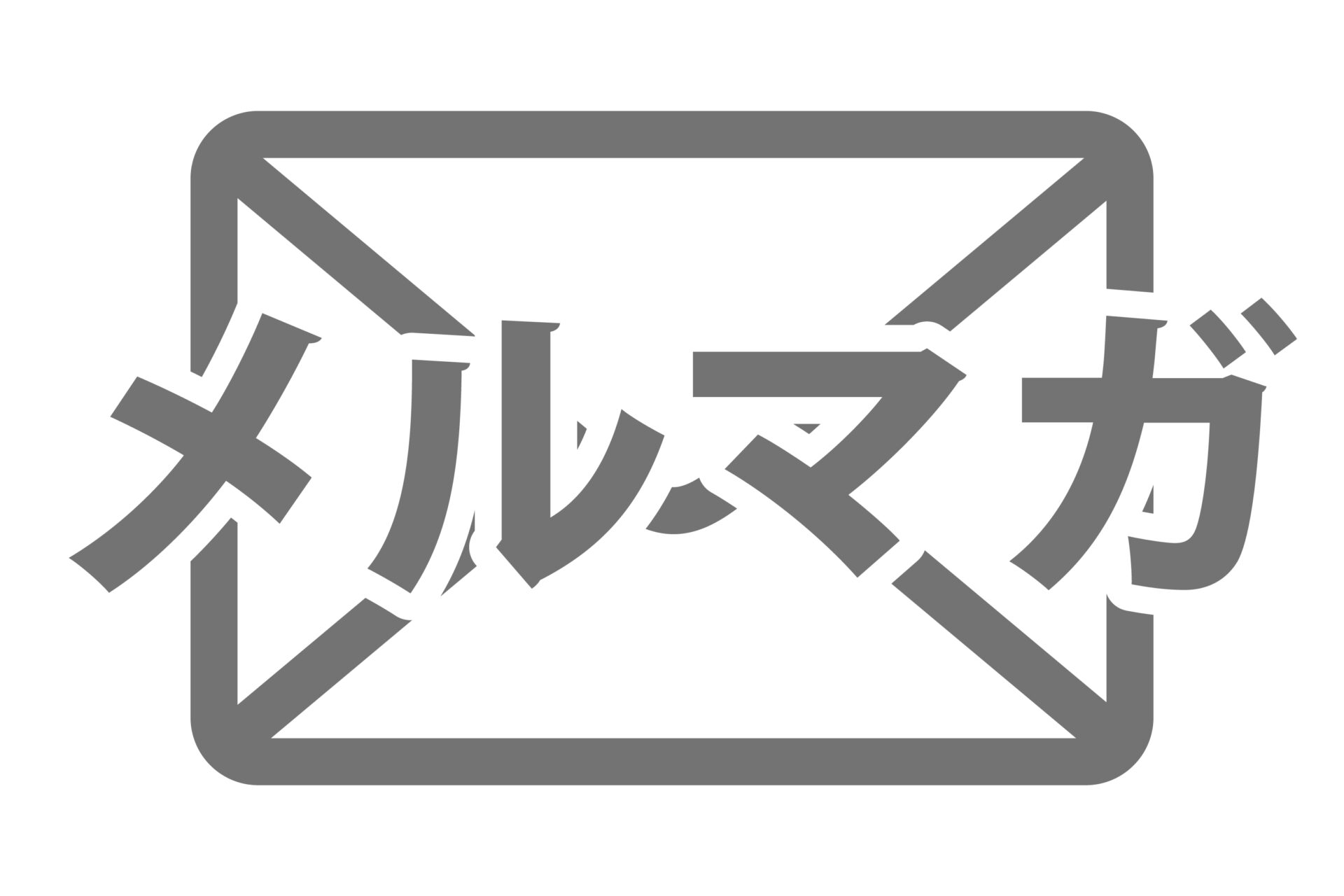17歳で早逝した山田かまちのノートに惹かれ、突如として日記をつけ始めたのが中学生のころ。並行して10代のあいだ書いていた雑記帳を今になっておそるおそる開くと、小さな日常が全てだった私の未熟さと、その裏返しである一途さとがないまぜになったものが、ページのあいだから濛々と立ち上ってきます。それは未だに、若々しいというよりは、生々しい。
「ぼくの血の言葉だけが真実だ」など、当時は知らないニーチェみたいなことが書かれているのは面白いけれど、基本的には誰かに見せられる内容でも質でもないノートたち。しかしその時期以後の私は、書くこと自体をしなくなりました。
日々を記録し、思いや考えを記すことが楽しかったというより、いくらたどたどしい筆致でも、何かを書き終わるたび、言葉が目の前に残って在ることにうれしさや安心がありました。それらの言葉は、何者でもない私を守ってくれるようでした。
ところがある時期から、日々の数行ですら書けなくなりました。書かれなければならないものがあるはずなのに、何を書けば、どのように書けば良いのか分からなくなりました。今日あったこと、今思っていることをそのまま書けば、それがそのまま私の足元を掘り崩してしまうように、日々を生きることの心もとなさや後ろ盾のなさを、書くことが増幅してしまうように感じるようになったのです。
書かれるべきことが書かれるために必要なのは、豊富な語彙でも、たくみな表現法でも、文字の多さでもありません。そこになければならないのはむしろ、書かれたことを静かに読み届けてくれる存在、そのことで書き手自身に自らの書いたものを読み届ける力を与えてくれる存在です。
何を書くべきか、どのように書くべきかということも、そうした存在が教えてくれることでしょう。そのような存在がないままに、書き手にとって意味を持つことは何ら書けないはずです。
何かと不遜な私がそれでも「恩師」と(今は)思えるかつての担任の先生から、10年近く前にもらったハガキが今も手元にあります。たしか、「好き勝手にやっていますが、先も見えず、何だかよく分からないことになっています。」みたいなことを、私が年始の挨拶がてら書いた返事でした。
表は彼が好きな山が全面に印刷されていて、ひっくり返すと宛名と住所の下に、「君の人生行路はこちらの期待にピタリと沿っています。健闘を常に祈っています。いつでも顔を出して下さい。」と、ごく短く、かつてよく見た癖のある字で書かれていました。そのときは「ふーん」と流し読んだその言葉を、その後、幾たび見返し、また思い出したことか。そのことの有り難さが、今になって分かります。
毎月書き重ねてきた本コラムも、今回でちょうど50回になります。まずは、他ならぬ自分のためであるような文章を書けています幸運に、あらためて感謝します。と同時に、恩師に限らず、50回の「書く」を近くで、遠くで、見届けてくれたと思うみなさんに、ささやかなお礼を記します。そして、願わくは私以外の方にとって、意味のあるものが書けていますように。
代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!